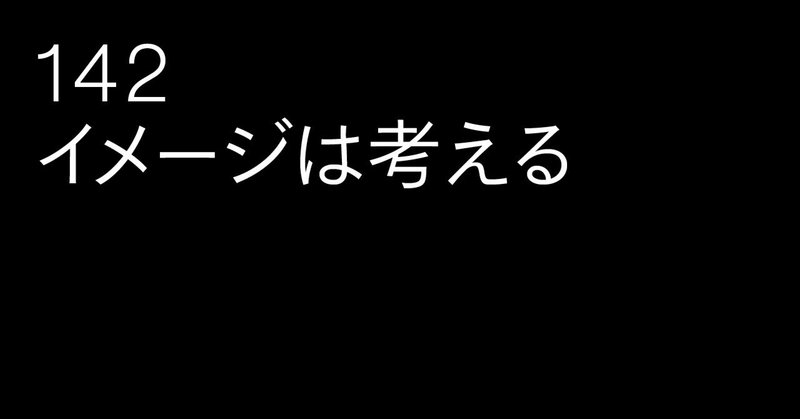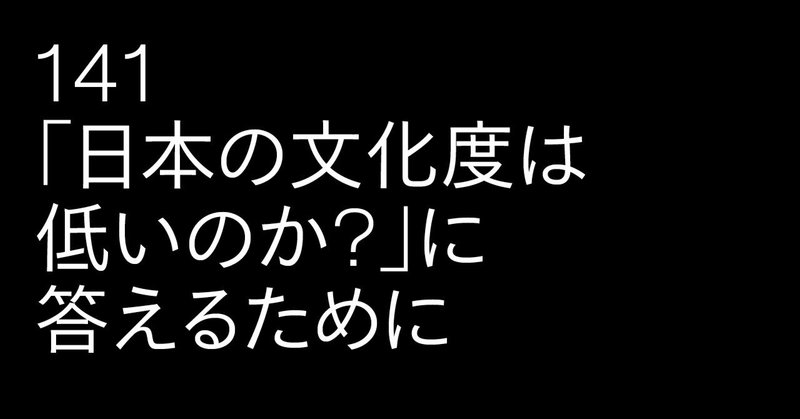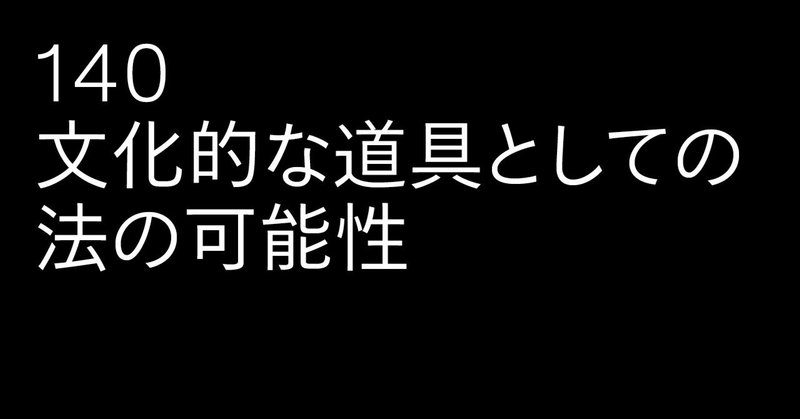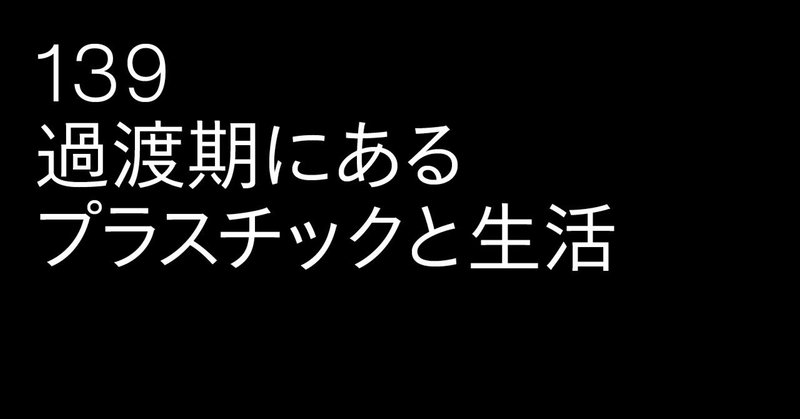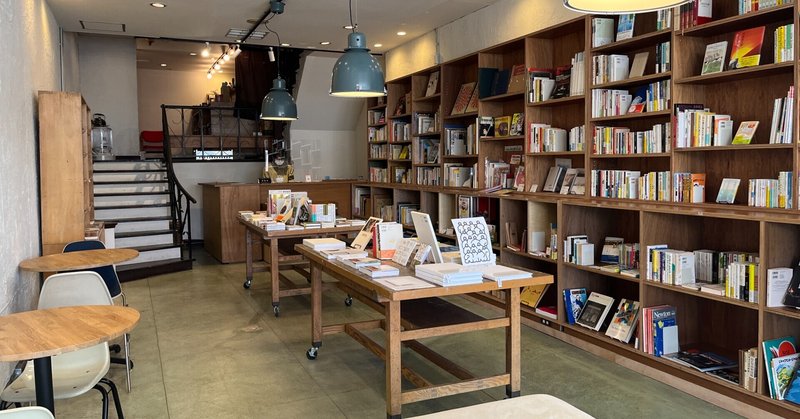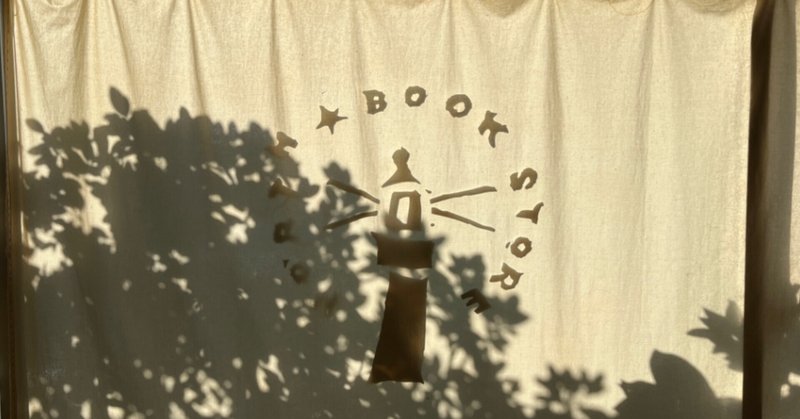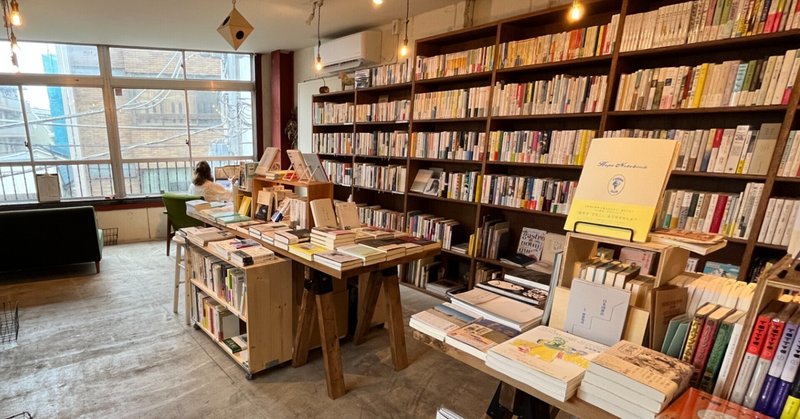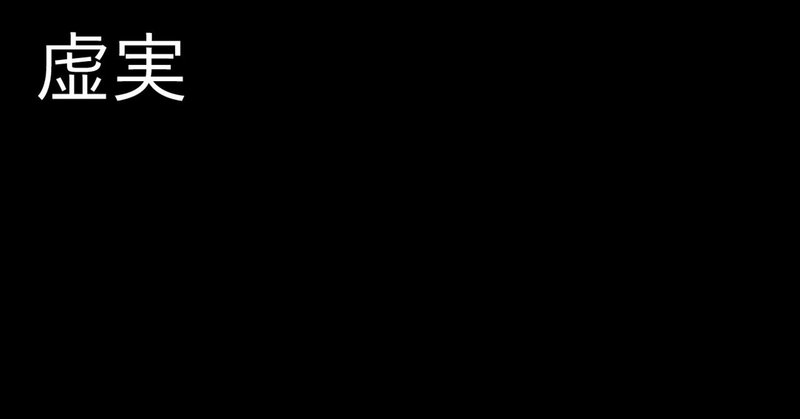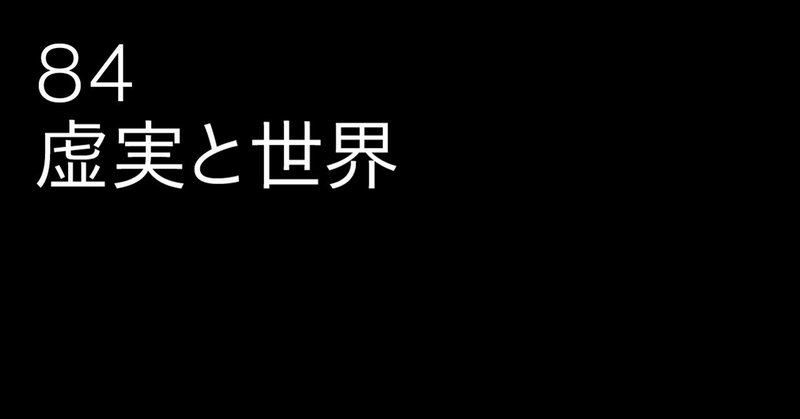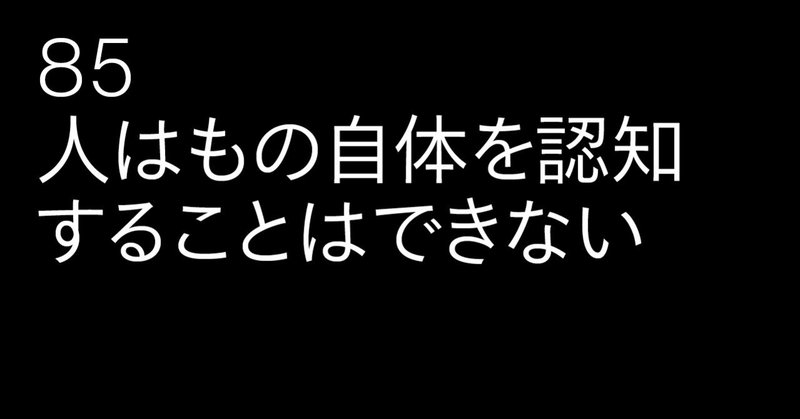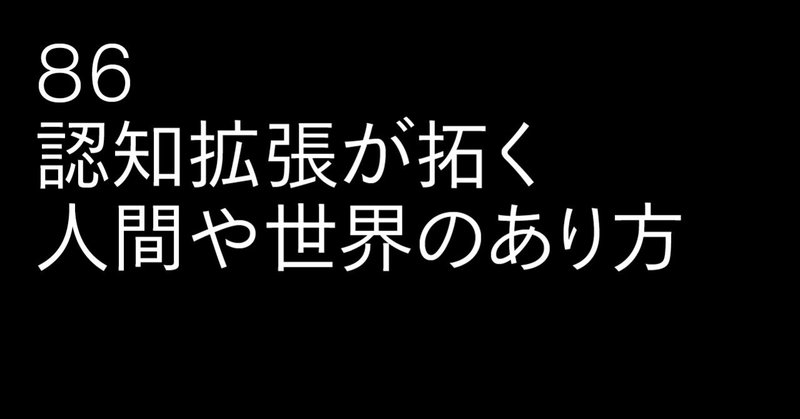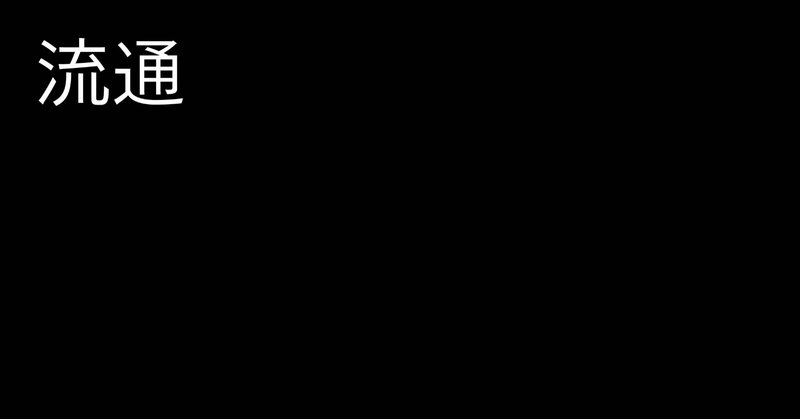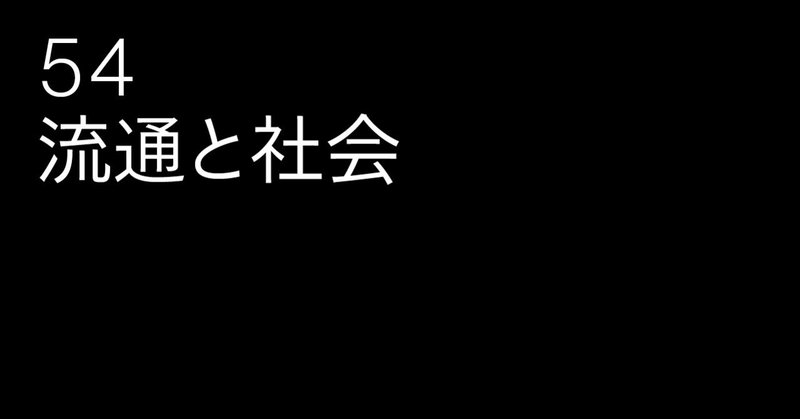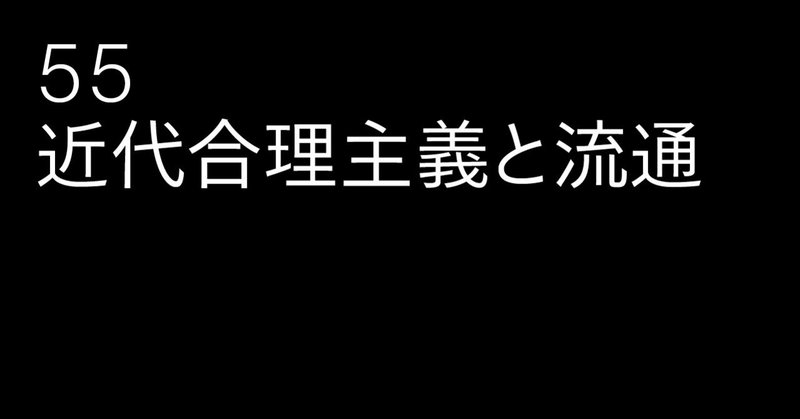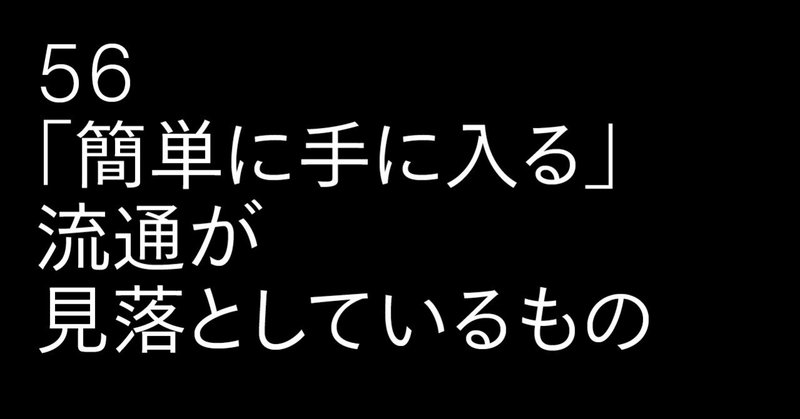雑誌『広告』
博報堂が発行する雑誌。「いいものをつくる、とは何か?」を思索する“視点のカタログ”として2019年にリニューアル創刊。クリエイティブディレクター/プロダクトデザイナーの小野直紀が編集長を務める。最新号の特集は「文化」。
『広告』文化特集号 全記事公開
2023年3月31日に発行された雑誌『広告』文化特集号(Vol.417)の全記事を公開しています。 (2023年8月24日追記)「124 ジャニーズは、いかに大衆文化たりうるのか」は、対談者・矢野氏の意向によりnoteでの全文公開を見送ることとなりました。ご了承ください。