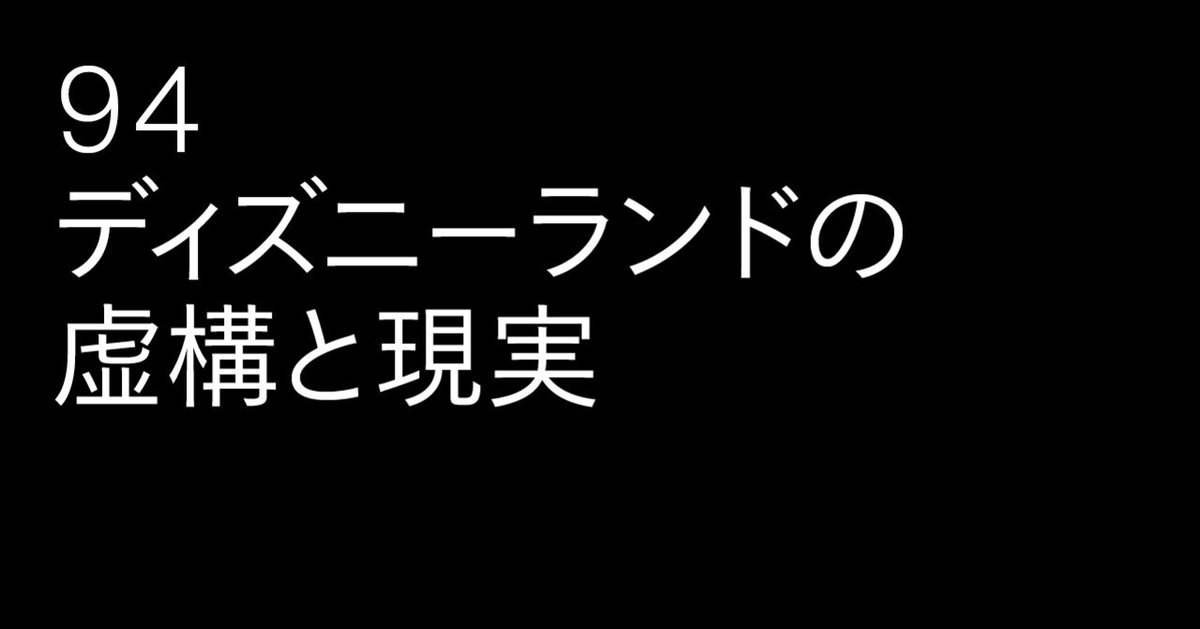
94 ディズニーランドの虚構と現実
1.はじめに
1983年4月15日、千葉県浦安市。
まだインターネットや携帯電話ですら、身近ではなかったこの時代。小雨の降るなか、真新しい入園ゲートの前には、約3,000人の客がその瞬間を待ちわびていた。まさかこの日が、日本の遊園地業界、さらにはレジャー産業を大きく変える節目になるとは、当時はまだ誰も想像すらしていなかっただろう。
午前8時45分、園内でセレモニーの壇上に立った、株式会社オリエンタルランドの高橋政知社長(当時)は高らかに叫んだ。
「1983年4月15日、ここに東京ディズニーランドの開園を宣言します!」
ウォルト・ディズニー・プロダクション(当時)が、米国以外で初めて手掛けたテーマパーク「東京ディズニーランド」が、ついに開園を迎えたのだった。いまでこそ日本一の入園者数を誇る、大人気のレジャー施設に成長したが、開園当時の反応は冷ややかだった。万国博覧会のように「半年で閉園する」といった噂や、土地を住宅地に転用して儲けようとしているのではないか、と成功を懐疑的に見る人間も多かった。もちろん、当時オリエンタルランドが掲げた「年間入園者数1,000万人」という目標に対しても、非現実的だとして信じる者は少なかった。
あれから38年。舞浜地区には世界で唯一、海をテーマにした「東京ディズニーシー」をはじめとして、ショッピングエリアやホテルが立ち並ぶ「東京ディズニーリゾート」が形成されている。ふたつのテーマパークの入園者数は、2018年度に過去最高の3,255万人を記録。単純に日割りすると、1日に9万人近くの人が訪れている計算になる。浦安市の人口の半分に当たる人々が、舞浜地区に毎日押し寄せているのだ。
では、どうして米国文化の象徴である「ディズニーランド」が、ここまで日本人に受け入れられたのだろうか。今回はディズニーランドの「虚構」と「現実」という視点から考察していきたいと思う。
2.なぜ、東京ディズニーリゾートに人が集まるのか
日常会話のなかで「ディズニー」と聞くと、多くの人は「東京ディズニーランド」「ディズニーのテーマパーク」を想像することが多いだろう。しかし、ディズニーとひとことで言っても、アニメーション映画にはじまり、実写映画、コミック、キャラクター、さらには稀代のクリエイターであるウォルト・ディズニー自身まで、その表す意味は多種多様なのだ。最近ではディズニー社が買収したマーベル・コミックや、ルーカスフィルムのコンテンツさえも「ディズニー」のなかに含まれている。それでも「ディズニー=テーマパーク」と多くの人が考えるということは、それだけ日本人にとっては東京ディズニーランドのイメージが強いということなのだろう。
なぜ、東京ディズニーリゾートに人が集まるのか。この疑問については、これまで多くの専門家が分析を重ねてきた。太平洋戦争の敗戦から、アメリカ文化への憧れがあったのではないか。高度経済成長から可処分所得が増え、ものよりも「体験」を重視する人が増えたからではないか。日本人が持つ「八百万の神」という考え方が、キャラクター好きを生み出したからではないか……ほかにも実に多面的な分析がなされてきた。そのうえで、ディズニーランドに人が集まるいちばんの理由は、現実を忘れさせ、虚構の世界を体験できるからではないか、と私は考えている。
なぜ、そう考えるのか。ここで時計の針を2010年に巻き戻すことにしよう。
当時、東京ディズニーシーの開園から10年近くたっていたが、ふたつのテーマパークを合わせた入園者数は、年間2,500万人台で頭打ちを続けていた。オリエンタルランドが今後の成長戦略を思い描いていたとき、日本を未曾有の大災害が襲う。2011年3月11日に東北地方の太平洋沖で発生した巨大地震、「東日本大震災」だ。
東京ディズニーリゾートは建物自体に被害を受けることはなかったが、舞浜地区を含む浦安市内で大規模な液状化が発生。地盤沈下などで大きな被害が出た。また、東京電力福島第一原子力発電所の事故による電力供給の不安定化、さらには放射性物質の飛散に対する不安から、東京ディズニーリゾートも臨時休園を余儀なくされた。
「千年に一度の大災害」「想定外」という言葉が多用されたが、この災害をきっかけに、つらい現実を目の当たりにした人も多かったのではないだろうか。とくに「日常は一瞬にして破壊されることもある」という危機感も、多くの人々の間で共有されたかもしれない。
日本国内を覆った自粛ムードの影響で、これまで左団扇だった東京ディズニーリゾートも集客に苦戦する事態に。これに対して、オリエンタルランドは、子ども用チケットの半額割引などを盛り込んだ「キッズサマースマイルキャンペーン」や、学生向けの割引チケット「キャンパスデーパスポート」の販売拡大など、様々な手を打っていった。地震発生から半年後の9月から始まった、東京ディズニーシー10周年イベントをきっかけに、少しずつ客足が回復。2011年度の年間入園者数は2,534万人と、なんとか2,500万人台に乗せることができたのだった。
しかし、事態は思わぬ方向に進む。
東京ディズニーランドでは、およそ5年ごとに「アニバーサリーイベント」を開催してきた。ファンの間では「周年イベント」と呼ばれる、大切な期間にあたる。それは販売商品やレストランメニューだけではなく、期間限定のショーやパレードにも力が入るからだ。もちろん、旅行代理店を中心に地方向けのキャンペーンも多く組まれる。
東京ディズニーリゾートでは2008年以降、東京ディズニーランドの周年イベントを、東京ディズニーシーを含めたリゾート全体で開催するようになっていた。これは、地方からの集客を考えた「きっかけづくり」の意味合いが大きかったと思う。
首都圏に住む人間にとって、東京ディズニーリゾートは自家用車や電車、バスなどでちょっと遠出すれば行ける距離にある。しかし、地方在住者にとって、東京ディズニーリゾートへ行くことは、まさに海外旅行にも匹敵する一大イベント。そんな地方在住者に対して「久しぶりに行ってみようか」という、きっかけを与えるのが周年イベントなのだ。リゾート全体で初めて周年イベントを開催した2008年。このときの年間入園者数は2,722万人と過去最高(当時)を記録し、あらためて集客力の高さを示していた。
ところが、2012年度の入園者数は、とくに周年イベントの開催などがなかったものの、年間で2,750万人を記録。2008年の記録を更新して、4年ぶりに2,700万人を突破したのだった。これは東日本大震災による自粛ムードが和らいだことに加え、現実を忘れさせてくれる、「非日常」を体験できる場所を求める人々が増えたからではないかと私は見ている。
2013年、東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランドの開園30周年を祝うイベントが開催されていた。これまでの周年イベントと同様に、首都圏だけではなく、地方からの来園客も増加。長年パークに通うファンからは、園内の混雑が激しくなっているという指摘も上がっていたほどだ。そして、ついにこの年、東京ディズニーリゾートは年間入園者数で大台の3,000万人を突破。過去最高を更新したのだった。
これまで2,500~2,700万人台で足踏みを続けていた数字は、2013年を境に3,000万人台を維持するように。東日本大震災の発生をきっかけに、東京ディズニーリゾートが持つ「非日常性」を求める人が増えていった、と考えるのが自然ではないだろうか。
さらには、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムといったSNSの急速な普及も、年間入園者数の急増の原因であると私は考えている。
東京ディズニーランドや東京ディズニーシーのチケット料金は、決して安くはない。園内で食事をしたり、お土産を買ったりすれば、それだけで大きな出費になる。さらに地方から訪れた場合は、交通費や宿泊料もかかってくる。決して頻繁に行けるような場所ではない。だからこそ、東京ディズニーリゾートを訪れること自体が「ステータス」になっている、という事実がある。
「イオンに行ったよ」と言っても、誰も感動はしてくれない。それは、イオンという商業施設が、日常の一部になっているからだ。その一方で「東京ディズニーリゾートに行ったよ」と言えば「うらやましい」「私も行きたい」と思う人は多いだろう。SNSが普及する以前は、親戚や友人、職場の同僚との間でしか「いいね」という声は共有されなかった。しかし、SNSによって、多種多様な人々から「いいね」をもらったり、送ったりするようになった結果、東京ディズニーリゾートは「他者から『いいね』をもらえる場所」になっていったのである。
SNSを見ていくと、リアルタイムで園内の情報を発信して、多くの人と共有しているアカウントがたくさん見つかる。なかには高額な撮影機材を準備して、プロ顔負けの写真を撮影している人もいる。これらすべてが承認欲求を満たすための行動だとは思わないが、少なくとも東京ディズニーリゾートをきっかけにして、他者に認められたい、他者よりも優位な立場を目指したい、と考えている人もいるのではないだろうか。
現実を忘れさせてくれる場所、非日常を体験させてくれる場所、承認欲求を満たしてくれる場所……。東京ディズニーリゾートは様々な面を併せ持つ。では、いかにして、東京ディズニーリゾートは「非日常」を実現しているのか。いよいよ今回の本題である、虚構と現実について考えていくことにしよう。
3.パークに入る前から「魔法」は始まっている
東京ディズニーリゾートへ行くとき、みなさんはどの交通機関を使うだろうか。家族連れで行く場合は、自家用車が多いだろう。友人同士なら、JR京葉線の舞浜駅で待ち合わせる、という方も多いかもしれない。
東京ディズニーリゾートの駐車場は、ほとんどの区画にディズニーのキャラクターが割り当てられている。これは広大な駐車場のなかで、自分がどの区画に車を停めたのか覚えやすくするためだ。しかし、それなら単に記号や数字だけでもよい。キャラクターを起用することで、日常と切り離し「東京ディズニーリゾートにやって来た」という気持ちを高めるという効果もある。
電車で来る場合はどうだろう。実は舞浜駅にある広告は、すべて東京ディズニーリゾートのものか、東京ディズニーリゾートの協賛企業(オフィシャル・スポンサー)のものに限られ、ディズニーの世界観をまとったものとなっているのだ。本来であれば舞浜駅はJR東日本の管理施設であり、オリエンタルランドが所有する施設ではない(施設改修費の一部はオリエンタルランドが負担)。仮に東京ディズニーリゾートと関係のない広告が並んでいたら、利用客は現実を思い出してしまう。駅からの導線も「非日常」への演出として、広告枠をオリエンタルランドが押さえていると考えられるのではないだろうか。
さて、メインエントランスから、園内に入ってみよう。あたりまえのようだが、東京ディズニーランドには客がとおる出入口は1カ所しかない。だが、日本国内にある公園や動物園、遊園地などでは、駅に近い出入口、駐車場に近い出入口といったように、複数の出入口を設けているところがほとんどだ。実はこれには深い意味がある。
ウォルト・ディズニーが、アメリカ・カリフォルニア州のアナハイムに「ディズニーランド」をオープンしたのは、1955年7月17日のことだった。彼はふたりの娘と遊園地に行ったときの経験から「大人も子どももいっしょに楽しめる場所をつくりたい」と考え、15年もの歳月をかけて歴史に残るテーマパークを生み出した。ウォルトはディズニーランドの設計にあたって、デンマークにあるチボリ公園などを視察するなどしたが、構造自体はそれまでの公園や遊園地にとらわれることがなかった。
アニメーターであり、映画監督でもあったウォルトは、それまでの映画製作のノウハウをディズニーランドの設計にも生かしていった。映画は始まりから終わりまで、ひとつのストーリーでつながっている。もし、出入口を複数にしたら、客はちぐはぐなストーリーしか体験できなくなってしまう。そう考えたウォルトは、ディズニーランドの出入口を1カ所にしぼったのだった。
「東京ディズニーランドは、アメリカのディズニーランドをそのまま真似してつくった」。これはファン以外でも聞いたことがあるかもしれない。実はこの逸話は厳密に言うと間違いがある。
ウォルトが唯一自身の手でつくり上げたのは、アナハイムにあるディズニーランドのみ。実は東京ディズニーランドは、ウォルトの死後にアメリカ・フロリダ州のオーランドに建設された「マジックキングダム・パーク」をモデルにしてつくられているのだ。ここはウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのなかに最初に建設されたテーマパークなのだが、実際にオーランドの地を訪れてみると、東京で見慣れた光景が広がっており、なんとも不思議な気持ちになる。
しかし、東京ディズニーランドは、マジックキングダム・パークをそっくりそのままコピーしたわけではない。東京ならではのデザインに変更されている部分もある。その代表的な例が、エントランスを入ってすぐにあるエリア「ワールドバザール」だ。
ここはお土産店やレストランなどが立ち並ぶエリアで、閉園時間近くになると、多くの来園客で混雑する。実はこのエリアにも、「非日常」をもたらす演出が隠されている。
入園ゲートをくぐって進むと、目の前にワールドバザールの大きな建物が迫ってくる。ここから、パークのシンボルであるシンデレラ城や、ほかのアトラクションを見通すことはできない。このような構造になっているのは、先ほども触れた「出入口はひとつ」というウォルトの考え方と同じで、客に対して「この先はどうなっているのだろう」とワクワクさせる構造になっているのだ。これは東京ディズニーシーなど、ほかのディズニーのテーマパークでも同様の構造になっている。
マジックキングダム・パークでは、アナハイムのディズニーランドと同じく、エントランスを入ってすぐの場所に鉄道の駅が設けられており、園内を広く見通すことはできない。客は線路の下にあるトンネルをくぐることで、夢と魔法の世界へと足を踏み込んでいくのだ。なぜ東京では、鉄道の駅ではなく、ワールドバザールの大きな建物で目隠しするようになったのか。この経緯については諸説あるが、一説には日本の法律上の問題から、園内を一周するような鉄道をつくることが難しかったから、ともされている。
さて、エントランスから園内の奥まで見通せないということは、園内から出口や外の世界も見通せなくなっていることを意味する。東京ディズニーランドを初めて訪れた人が困ることのひとつに「出口がどこかわからない」という問題がある。だが、これは外の世界を隠すことで、ディズニーランドがつくった世界に客を没入させやすくしているのだ。
東京ディズニーランドに入ると、園内から東京ディズニーリゾートとは無関係の建物は見えにくくなっている。これも、虚構の世界に没入させやすくするための工夫だ。パークの周辺には「バーム」と呼ばれる盛り土がされており、背の高い木を植えることで、周囲の建物を見えにくくしている。東京ディズニーシーでは、逆に東京湾に近い部分を開けることで、まるで本物の海とつながっているように感じられる構造になっている。これは「借景」と呼ばれる手法で、緻密な設計をもとに実現しているのだ。
ただ、どうしても客の目から隠せないものもある。園内にあるスピーカーや管理用の施設などがその代表例だ。しかし、こういった隠しにくいものでも、ディズニーらしいこだわりがある。それは「ゴーアウェイグリーン」と「ブレンディングブルー」と呼ばれる塗料だ。ディズニーのテーマパークでは、目立たせたくないものや客の視界にとって邪魔になるようなものは、緑色で塗られていることが多い。東京ディズニーランドの園内にある、スピーカーなどを観察するとわかりやすい。また、建物の壁には緑色のほかに、空の色に溶け込みやすくするために青色が使われていることもある。
客が「非日常」に没入しやすくする仕組みとして、ウォルトの映画人としてのノウハウはほかにも見つけることができる。そのひとつが「強化遠近法」だ。これは、映画のセットづくりでも使われている方法で、目の錯覚を利用して、建物をより大きく見せたり小さく見せたりする方法を指す。
先ほども触れたワールドバザールでは、建物の1階と比べて、2階や3階の高さが低く設計されている。これは設計ミスではなく、上に行くほど低くすることで、実際よりも高く感じさせるための工夫なのだ。同様の構造はシンデレラ城など、ほかの園内の建物でも見つけることができる。
4.客が「想像しやすい」「没入しやすい」空間設計
東京ディズニーランドには、7つのテーマランドがある。
ウォルト・ディズニーが生まれ育った20世紀初頭のアメリカが再現されている「ワールドバザール」、冒険とロマンの世界「アドベンチャーランド」、19世紀に開拓時代を迎えたアメリカ西部が再現されている「ウエスタンランド」、小動物たちが暮らす「クリッターカントリー」、ディズニー映画のキャラクターたちに出会える「ファンタジーランド」、ミッキーやその仲間たちが暮らす「トゥーンタウン」、そして近未来を体験できる「トゥモローランド」だ。
こうやって見ていくと、東京ディズニーランドのエリアは、実際にある場所を再現したり、参考にしたりしているエリアと、ディズニー映画や空想上の世界をテーマにしたエリアのふたつに分けることができる。
実際にある風景を再現したエリアであれば、タイムスリップしたような感覚や、まるで世界旅行を体験しているような感覚を味わうことができる。仮に世界史などの知識がなかったとしても、「カリブ海にはこんな海賊がいたんだ」「西部開拓時代は大変だったんだな」というように、これまでの生活経験をもとに、その世界を想像することができる。だからこそ、その世界の一員として、非日常への没入感も大きくなっていく。
もし、これが「25世紀の太陽系外惑星をイメージしたエリアです」と言われたら、果たして客は楽しめるだろうか。いくら空想上の世界だとしても、25世紀の世界を想像することは難しいし、地球以外の惑星について知っている人間は少数派だろう。ここがディズニーのテーマパーク設計で非常にレベルが高い点なのだ。客が「想像しやすい」「純粋に物語の世界に没入しやすい」という点に重点を置いているからこそ、一見するとバラバラなエリア構成にも体験的な統一感が生まれるのである。
ディズニーが製作するアニメーションや実写映画は、日本をはじめ世界各国で人気を集めている。しかし、東京ディズニーランドを訪れるすべての客が、ディズニー映画を観たことがあるとは限らない。その点でも、ディズニーのテーマパークは抜かりがない。仮に映画のストーリーを知らなくても、施設単体だけでも充分に楽しめるように構成されているのだ。施設によっては、映画のストーリーを追体験できるものだけではなく、映画のサイドストーリーとして設計されている場所もあるため、「映画はほとんど観たことがある」というコアなファンでも楽しめるようになっている。
もちろん、日本で生活していれば、ディズニーのキャラクターやプリンセスを目にする機会は当然ある。「映画は観たことがなかったけど、この作品ってこんなストーリーなんだ」とわかってもらえれば、映画やテレビシリーズを視聴するきっかけになるかもしれない。こんなところにも、ディズニーの緻密な戦略が感じられる。
ディズニーのテーマパークには、ほかにも客が非日常に没入しやすくするための仕掛けが隠されている。園内には、様々な場所に個性あふれるトイレが設置されているが、実は女性用も男性用も、手洗いのところに鏡がつけられていない(一部例外の場所もある)。これは、髪型やメイクを直す客で手洗いが塞がれるのを防ぐためという理由もあるのだが、ふと鏡で自分の姿を見て、現実を実感しないようにするため、という心理的な効果を狙っている。また、園内には必要最低限の数の時計しか設置されていない。これも時刻を見て、客が現実に引き戻されるのを防いでいるのだ。
乗り物やシアター系の施設に入るときに、一部の施設では「プレショー」と呼ばれる、簡単な演出が用意されている。東京ディズニーランドでは、999人の幽霊たちが住む「ホーンテッドマンション」のストレッチングルームや、東京ディズニーシーにあるフリーフォール系ライド「タワー・オブ・テラー」のハリソン・ハイタワー三世の書斎などがその代表例だ。あくまでも乗車する前のちょっとしたお楽しみなのだが、その施設のテーマや登場人物について紹介され、客は一気に物語に引き込まれるような仕掛けになっている。
それ以外の施設でも「キューライン」と呼ばれる待機列の途中に、様々な展示やボードが用意されているところもある。客は単に乗車までの時間つぶしをするだけではなく、自らもその施設の世界に登場するキャラクターという実感がわいてくるのだ。
また、本物へのこだわりも客を「非日常」の空間へ引き込むためにひと役買っている。いくら実際にある風景を再現していても、見た目が雑であったり、陳腐なものであったりしたら、客はがっかりしてしまうだろう。一気に現実へ引き戻されてしまう。しかし、ディズニーが手掛けるテーマパークでは、徹底した調査と設計、さらには潤沢な資金を注いで、細部にまでこだわってつくられている。
たとえば、東京ディズニーランドに掲げられている、アメリカ合衆国の国旗。時代によって州の数が異なるため、旗に描かれる星の数はそれぞれ違うデザインになっている。園内ではいくつかの場所で星条旗を見つけることができるのだが、エリアや建物の時代設定に合わせて、その当時の星条旗を再現しているのだ。思わず見逃してしまうようなところにも、細かなこだわりが感じられる。
もうひとつの例は、シンデレラ城の中央通路にある、映画『シンデレラ』のストーリーが再現されているモザイク壁画。実はこの壁画の一部には、本物のダイヤモンドが使われているのだ。予算を考えれば、代用品や普通のガラスでもよかったはず。しかし、この細部へのこだわりが、夢と魔法の基礎を形づくっていることを、ディズニーの人間たちは知っているのだ。
細部へのこだわりは、東京ディズニーシーでも見つけることができる。パーク中央にあるプロメテウス火山。ここは活火山のため、熱水噴出孔があるのだが、実際に反射温度計で測ってみると本当に高温のお湯が噴き出しているのだ。客は触れられない距離にあるため、仮に水でもわからないはずなのに。このほかにもプロメテウス火山では、実際に火山で見られる「パホイホイ溶岩」を再現しているなど、火山学者が研究材料に取り上げるほどの完成度を誇っている。また、園内の「アメリカンウォーターフロント」には、同じエリア内でもガス灯と電灯の2種類の違う街灯が再現されている。これも細かな時代の変化を再現しているのだ。
こうしたディズニーのテーマパークの設計は、ディズニー社が誇る「イマジニア」と呼ばれる人々が支えている。これはウォルト・ディズニー・イマジニアリングで働く従業員の総称で、「イマジネーション」と「エンジニア」を組み合わせたディズニーの造語だ。
イギリスのSF作家として知られるアーサー・C・クラークは、かつて自身の著書『未来のプロフィル』のなかで3つの法則を提唱している。この「クラークの三法則」のひとつに「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」がある。東京ディズニーランドは一見するとファンタジーな虚構の世界にも思えるが、実際にはイマジニアたちの徹底した技術開発で支えられていることは、あまり知られていない。
イマジニアたちが開発した技術で、もっとも代表的なものが「オーディオアニマトロニクス」と呼ばれる技術だ。オーディオ、アニメーション、エレクトロニクスを組み合わせた造語で、コンピューターによって、音に合わせて精密にロボットを動かす技術を指す。
この技術が最初に開発されたのは、1963年のこと。アナハイムのディズニーランドに導入された「魅惑のチキルーム」では、鳥や花たちが音楽に合わせて歌い踊り、客をおおいに楽しませた。その後もウォルトとイマジニアたちは研究開発を続け、1964年に開催されたニューヨーク万国博覧会では、のちにディズニーランドに移設された「イッツ・ア・スモールワールド(ペプシコーラ提供のユニセフ館)」など複数のパビリオンでその技術が一気に花開いた。現在ではさらに技術革新が進み、2020年9月に東京ディズニーランドにオープンした最新施設「美女と野獣“魔法のものがたり”」でも採用されている。
まるで本物の動物や人間と同じように動く姿からは、ロボットという実感はない。本当に目の前に存在しているという感覚さえある。これも非日常の世界への没入を高めていると言えるだろう。
5.夢と魔法の空間を支える「キャスト」
ここまで、東京ディズニーリゾートがどのように「非日常」を演出しているのか、主にハード面から考察してきた。ここからは、テーマパークで働く従業員に注目していきたい。
先ほども触れたとおり、ディズニーランドは映画人であったウォルトが、映画製作のノウハウを生かしてつくり上げた場所である。そのため、園内は「大きなひとつの舞台」であり、客がいる場所は「オンステージ」、その逆で園内の維持管理に使われる場所や、従業員が休憩時間を過ごすための場所は「バックステージ」と呼称している。ウォルト・ディズニーは、従業員が制服を身に着けたまま、異なるテーマのエリアのなかを移動して客の目に触れることがないよう、従業員導線に配慮するほどの徹底ぶりだった。
また、従業員のことは映画の出演者である「キャスト」、入園客はカスタマーではなく「ゲスト」と定義している。いまではファン以外でも「キャスト」「ゲスト」という呼び名を使う人も多くなっており、一般的な認知度は高いかもしれない。
このように、アルバイトの従業員ですら「ディズニーの世界をつくり上げる出演者」という定義がされている。ここにも東京ディズニーリゾートが日本一の入園者数を誇る理由がある。いくら施設が立派であっても、乗り物や土産物店、レストランの従業員のサービスが悪ければ、多くの客が「がっかり」「価格に見合う価値がない」と感じるだろう。しかし、東京ディズニーリゾートでは、キャスト一人ひとりが客の夢と魔法を壊さないように、日々奮闘している。私自身、アメリカをはじめ、世界各国にあるディズニーのテーマパークを訪れたが、東京のサービスレベルが「世界一」だとお世辞抜きで言えると思っている。
では、一体キャストたちは、どのように非日常を演出しているのだろうか。
東京ディズニーリゾートはアメリカのウォルト・ディズニー・カンパニーによる運営ではない。ディズニー社とライセンス契約を結んだ、株式会社オリエンタルランドが管理・運営を担っている。
オリエンタルランドの従業員は、全部で約2万人。そのうち正社員は5,000人強で、それ以外の約15,000人は準社員、いわゆるアルバイトなのだ。しかし、それぞれのキャストが自分の与えられた役割を、忠実に演じているのがわかる。施設のテーマに合ったコスチュームを身にまとい、乗り物やレストランの世界観、時代設定に合わせた接客をする。イタリアであれば「チャオ」や「ボンジョルノ」を使う。昼間であっても、施設の時間設定が夜であれば、「こんにちは」ではなく「こんばんは」で挨拶する。単なる従業員ではなく、一人ひとりが「ジャングルを探検する船長」や「博物館の学芸員」になりきることで、客は虚構の世界へと没入していくのだ。
もちろん、ホスピタリティにあふれる、心温まるサービスの提供は言うまでもない。笑顔での声掛け、清潔感のある身だしなみ、こまめな挨拶やお手振り、バースデーシールを着けた客へのお祝いなど、その内容は枚挙にいとまがない。
キャストによるサービスには、通常の接客業務に加えて「マジカルモーメント」と呼ばれる特別なものもある。たとえば、東京ディズニーシーでは毎朝の開園時に、ミッキーマウスやミニーマウスによる短いセレモニーが行なわれる。実はこのセレモニーには、キャストに選ばれた客が出演者として参加できるのだ。1日1組限定、客は入園ゲートのキャストに合図を出したあと、ミッキーやミニーと特別な時間を過ごすことができる。このほかにも、抽選制のショーへの優先案内、特別な場所でのショー観賞など、現在は廃止されたものもあるが、様々なサービスが行なわれている。似たようなものとして、2018年の東京ディズニーランド35周年イベントでは、「ハピエストサプライズ」と題し、キャストに選ばれた特定の客に対して、特別なサービスが行なわれたこともある。
マジカルモーメント以外にも、東京ディズニーリゾートには「ピクシーダスト」と言って、困っている客への救済措置が用意されている。これはキャストがそれぞれ持っているカードに、特別なサービスを書き込んで、客に渡すというものだ。たとえば、小さな子どもが食べ物を落としてしまったとき。現場を見ていたキャストが、代わりのものを無料でもらえるように、ピクシーダストのカードを書いてくれることがある。また、並んでいた乗り物が突然止まってしまって、持っていた施設の優先案内券が時間切れになってしまったとき。これも、現場のキャストの判断で、有効時間を延ばしたピクシーダストのカードを準備してくれることがある。それ以外にも、風船の紛失や商品の破損など、客に過失がない場合に、キャストが現場の判断で救済してくれるのだ。
ただ、最近ではSNSの普及に伴って「同じお金を払っているのに不公平では」「基準が不明確」といった批判の声があるためか、サプライズ的なサービスは縮小傾向にあるように感じられる。しかし、こういった「特別なことをしてもらえた」という満足感は、次回以降の来園につながると言えよう。
さらには、裏側から現場を支えているキャストの存在も忘れてはいけない。東京ディズニーリゾートでは、施設の保守点検などを徹底して行なっており、客が安心して楽しめるように努力を続けている。東京ディズニーランドでは、1983年の開園以来、整備不良が原因による死亡事故は1件も起こっていないことからも、その安全性が証明されている。もし乗り物が汚れていたり、いかにも壊れそうなものだったりすれば、客はがっかりして現実の世界に引き戻されてしまうだろう。身の危険を感じて、楽しめなくなってしまうかもしれない。だからこそ、安心・安全がいちばん重要なのだ。
また、園内では「カストーディアルキャスト」と呼ばれる、清掃専門の従業員が多く配置されている。トラッシュ缶と呼ばれる大型のごみ箱も多数設置されており、客がポイ捨てして園内が汚れないような仕組みが整えられているのだ。これは、それまでの遊園地に清潔さが欠けていたことを嘆いていたウォルトが、園内の清潔さに強くこだわっていたという背景がある。ウォルトは従業員に対して「いつもきれいにしておけば、お客は汚さない。でも、汚くなるまでほっとけば、客はますますゴミを捨てるものだ」という格言を残しており、その教えは東京ディズニーリゾートでも忠実に守られている。
さらにパークの清掃作業は、閉園後にも続けられている。「ナイトカストーディアル」と呼ばれる仕事では、客のいなくなったパークで水をまき、地面や施設を徹底的にきれいにしていくのだ。テレビ番組でも取り上げられたことがあり、最近ではファン以外でも知っている人が増えているのではないだろうか。このような地道な作業があるからこそ、つねに清潔なパークが保たれているのだ。
もし、園内にごみが散乱していたら、客はどう思うだろうか。いくら施設が立派だったとしても、ほころびが感じられて、一気に冷めてしまうかもしれない。こんな細かなところへのこだわりも、夢と魔法の実現を支えている。
表側・裏側双方の従業員の根底にあるのは、「SCISE」と呼ばれる、ディズニーテーマパークにおける行動基準だ。これは東京ディズニーリゾートをはじめ、世界各国にあるディズニーのテーマパークでも同様に掲げられており、まさにディズニーの憲法とも言うべき存在かもしれない。
「SCISE」は、Safety(安全)、Courtesy(礼儀正しさ)、Inclusion(包含、一体性)、Show(ショー)、Efficiency(効率)の5つの頭文字となっており、Inclusionが規準の中心に位置付けられている。
安全を優先すべきなのは当然だが、礼儀正しさはウォルトがかつて語った「すべてのゲストがVIP」という考え方にもとづいている。性別、人種、年代、出身地を問わず、それぞれの客に合ったサービスを提供することが求められている。また「ショー」には、単に演じるという意味だけではなく、「毎日が初演」という理念にもとづき、つねに緊張感を持って仕事に取り組むことが目標とされている。
なお、これまでの行動規準は「SCSE」だったのだが、2021年4月に新たな鍵としてInclusionが追加された。ディズニーでは近年、ポリティカル・コレクトネスを重視しており、差別や偏見、少数派への配慮として、Inclusionの追加を決めたのだろう。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドも、2021年12月にInclusionを追加した新たな行動規準「The Five Keys〜5つの鍵〜」を発表している。
安全・安心・清潔だからこそ、客は虚構の世界を思う存分楽しむことができる。ハード面だけではなく、ソフト面で夢と魔法の空間を実現しているのは、現場にいる一人ひとりのキャストだということは間違いない。
6.なぜ、人はつくられた「非現実」に没入するのか
最後に、ディズニーのテーマパークにおける「虚構」と「現実」を考えるなかで浮かんだ、ひとつの疑問について考えていきたい。なぜ、人は虚構だとわかっているにもかかわらず、ディズニーランドというつくられた非現実に没入するのだろうか。この答えを探るべく、ふたりの専門家に取材した。ひとりめは、社会心理学者の諸井克英氏。ミュージシャンのライブになぞらえて解題してくれた。
ミュージシャンにはそれぞれの「世界観がある」とよく論じられます。私たちは、ライブに行くとき、会場に行ってそのミュージシャンの歌を初めて聞くのではなく、CDやインターネットなどで彼らが繰り広げる物語を充分に事前に探索して、その世界観を自分のなかに構築します。そのうえで、ライブでその世界に没入するのです。
ディズニーランド来園の場合も同じ原理です。事前に記憶している物語世界が重要です。本やアニメーション映画などで充分に既知である物語世界が目の前に繰り広げられることで、来園者はディズニーランドの世界に没入します。
また、この没入の本質は、パーク側と来園者側との「共犯関係」の成立にあります。来園者は、パーク側の仕掛けに対して受動的に虚構の世界に入り込んでいくというより、あたかも「共犯」者のごとく自らを能動的に組み込んでいくのです。さらに、来園者同士もパークのなかで協応しながら「共犯関係」をつくりあげていきます。それは、音楽ライブのように、演者と観客が一体化して盛り上がることでひとつの音楽経験が生じる構造と類似しています。
つまり、目の前の世界が「真実かどうか」はもはや問題ではありません。あえて言えば、来園者は、虚構であることがわかっていながら、幻想的世界へと巻き込まれていくのです。これが「虚構世界の現実化」です。
園内にいるミッキーマウスを、ただの「着ぐるみ」と真偽判断するのではなく、「真実のキャラクター」として積極的に認識します。つまり、虚構世界へと没入するなかで「虚構と現実の融合」という快楽に浸るのです。これがディズニーランド来園動機の本質です。
続いて、日米消費文化論の研究者であり、講談社『ディズニーファン』における「ディズニー・アカデミー」の執筆や、言語・文化学の見地からパーク解説を行なっている関口英里氏に取材をした。ディズニーランドにおける虚構性を人々はどう受け止めているのか、次のように語った。
ディズニーランドを虚構と現実という二項対立で語るのは、不適切かもしれません。私たちの現実社会はすでに虚構化しており、リアルなものは実は何もないと言えます。そのなかで東京ディズニーランドは徹底的に虚構を現実化しています。すでにそれらが「真の本物」になっている以上、何が虚構で何が現実かを考えるのは難しいでしょう。
「虚構と現実」という単なる二項対立ではなく、さらに言うと、東京ディズニーランドは日常の延長線上にあって、いつもとは違う自分を演じることができる場所になっているのではないでしょうか。完璧なセットつきのステージとして、日常から抜け出すことができる「脱日常の舞台装置」としての役割があると考えられるのです。そこで、単なる客ではなく、自らがパークの一部となって自発的に演じることで物語が成立していく。パークで働くスタッフたちはそもそも物語の一部、演じ手として設定されているからこそ「キャスト」と呼ばれています。同時に「ゲスト」と呼ばれる来園者も実は演じ手としての「キャスト」であるとも言えます。しかし、そこには台本や演技指導などはまったくありません。ゲストは自ら行間を読んで「ここではこう振る舞うべき」「こういう自分であるべき」という不文律を構成し、東京ディズニーランドにふさわしいペルソナを演じている、という予定調和の物語が自動的に成立していると考えられるのです。
ディズニーが追求しているのは、現実に存在するものを再現する「リアリティ」ではなく、あくまでも人々が想像した「イメージ」を徹底的に再現しているだけです。たとえば、「リアル」な動物を見たいなら本来は動物園に行くのが「正解」と言えます。しかし、動物たちは私たち人間の想像したとおりの動きはしてくれません。昼間であれば、ずっと寝ていることもあるでしょう。これに対して、東京ディズニーランドにあるアトラクション「ジャングルクルーズ」では、つねに動物たちは私たちの思い描いたとおりの動きをしてくれます。イメージに現実が追随する現代社会だからこそ、人々はディズニーランドの動物たちこそが「リアル」だと感じ、わくわくしながら辛抱強く数時間待ちの列に並ぶのです。
7.おわりに
2020年春から突如巻き起こった、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行。東京ディズニーリゾートは東日本大震災以来、2度目の臨時休園を余儀なくされるなど、大きな打撃を受けた。しかし、東日本大震災によって、つらい現実を目の当たりにした人々が「非日常」の空間を求め、東京ディズニーリゾートに押し寄せたという見方もある。この感染症の流行が収束すれば、再び東京ディズニーリゾートには、多くの客がやって来るだろう。もちろん、日本国内だけではなく、海外からも多くの人々がやって来るに違いない。自由にパークへ行けるようになったときには、夢と魔法の空間は、様々な人々の努力によって支えられている、ということを頭に入れながら、楽しんでもらえれば幸いである。
文:立花 陽菜
立花 陽菜 (たちばな ひな)
幼少期にディズニーのアニメーションと出会い、ミッキーマウスをこよなく愛するジャーナリスト。東京ディズニーランドには、開園10周年イベントをきっかけに、足かけ30年近く通い続けている。2013年3月に、はてなブログ「舞浜新聞」を始動。パーク&リゾートに加えて、実写映画、アニメーション映画、ミュージカル、コンサート、マーチャンダイズなど、様々な「ディズニー」を追いかけている。
諸井 克英 (もろい かつひで)
博士(心理学)。静岡大学人文学部社会学科教授を経て、現在、同志社女子大学生活科学部・人間生活学科・特任教授。主な著書は『孤独感に関する社会心理学的研究』(風間書房)、『夫婦関係学への誘い』、『ことばの想い』(ともにナカニシヤ出版)、『ハイロウズの掟』、『動物園の社会心理学』(ともに晃洋書房)。2021年春に『表象されるプロレスのかたち』(ナカニシヤ出版)を公刊。
関口 英里 (せきぐち えり)
同志社女子大学学芸学部メディア創造学科教授。博士(言語文化学・大阪大学)、M.A. in American Studies (Pennsylvania State University)。専門は日米の消費文化論、近現代社会におけるメディア文化論。都市を中心とした様々な「文化装置」分析の視点からテーマパークやイベント研究に携わり、関連業績も多数。また産官学連携で地域社会・文化の活性化プロジェクトも推進している。著書に『現代日本の消費空間──文化の仕掛けを読み解く』(世界思想社)、『ヴァナキュラー文化と現代社会』(思文閣)ほか。現在『ディズニーファン』(講談社)にてパークに関する解説「魔法のディクショナリー」を連載中。
参考文献
『ディズニーランドという聖地』(能登路雅子、岩波書店、1990年)/『ディズニーの魔法』(有馬哲夫、新潮社、2003年)/『原発・正力・CIA──機密文書で読む昭和裏面史』(有馬哲夫、新潮社、2008年)/『ディズニー五つの王国の物語』(有馬哲夫、宝島社、2009年)/『ディズニーランドの秘密』(有馬哲夫、新潮社、2011年)/『増補版 ディズニーランドの経済学』(粟田房穂、朝日新聞出版、2012年)/『新版ディズニーリゾートの経済学』(粟田房穂、東洋経済新報社、2013年)/『ディズニー 夢の王国をつくる』(マーティ・スクラー、河出書房新社、2014年)/『海を超える想像力──東京ディズニーリゾート誕生の物語』(加賀見俊夫、講談社、2003年)/『“感動”が人を動かす』(堀貞一郎、竹井出版、1992年)/『Door of Dream──東京ディズニーランド超ガイド』(講談社、1996年)/『ディズニーランド流心理学「人とお金が集まる」からくり』(山田眞、三笠書房、2002年)/『東京ディズニーランドをつくった男たち』(野口恒、ぶんか社、2006年)/『ディズニーランドが日本に来た!』(馬場康夫、講談社、2013年)/『ディズニーランドはなぜお客様の心をつかんで離さないのか』(芳中晃、中経出版、2004年)/『女性がディズニーランドを愛する理由』(芳中晃、中経出版、2005年)/『ディズニー化する社会』(アラン・ブライマン、明石書店、2008年)/『ディズニー7つの法則 新装版』(トム・コネラン、日経BP社、2014年)/『都市と消費とディズニーの夢』(速水健朗、角川書店、2012年)/『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』(ニール・ゲイブラー、ダイヤモンド社、2007年)/『柳生すみまろのディズニーランド誕生秘話』(柳生すみまろ、講談社、2011年)/『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』(ディズニー・インスティチュート、日本経済新聞出版、2018年)
_______________
この記事は2022年3月1日に発売された雑誌『広告』虚実特集号から転載しています。
また、『広告』虚実特集号は、Amazonおよび全国の書店で引き続き販売中です。
> 販売店一覧
最後までお読みいただきありがとうございます。Twitterにて最新情報つぶやいてます。雑誌『広告』@kohkoku_jp

