
23 高予算の駄作はなぜ生まれるのか 〜 日本の映画業界が向かう先
スケールの大きい高予算の映画、でも観てみるとなんだかガッカリ……なんて経験をしたことがある方は多いのではないか。一方で、昨年の大ヒット作『カメラを止めるな!』のような低予算でおもしろい作品もたくさんある。そもそも低予算での製作は、どんな名監督もとおってきた道だ。それがなぜ高予算になった途端に、質が下がるケースが頻発してしまうのか? もしかするとそこには、高予算特有のネガティブな構造があるのではないか?
近年、河瀨直美監督作品をはじめ、上質な作品を製作し続けるキノフィルムズの社長・武部由実子氏に映画業界の実情を聞いた。キノフィルムズは、まだ業界内で忖度がはびこるなか、「新しい地図」の3人それぞれの主演映画を製作するなど話題はつきない。また武部氏はプロデューサーとしても現役で、最近では草彅剛主演作品『台風家族』を手がけたばかりだ。
企画決定のプロセスに、高予算の構造的な問題があった
── 早速ですが、映画製作において、高予算特有の構造的な問題は存在しているのでしょうか? たとえば、製作を進める上で、口を出す人が増えてしまうなど……。
そこは、予算はあまり関係ないですね。たとえば、高予算だからと言って、脚本を変更しないといけないわけではなくて、逆に予算が低いからといってそれが勝手にできるかっていうとそうでもなくて。仮に、三谷幸喜オリジナル作品に博報堂が出資していたとして、博報堂の人が意見を言えるのか。たぶん否だと思う。
もっと言えば、だいたい出資を募るときって、本(=脚本)ありきでやるんですね。「この本でどうでしょう? お金出しませんか?」ってやるので、出資の前提としてその本に“乗っている”という状態になっている。じゃあお金を出すか出さないかの判断のときに「ここがこう変われば出してもいい」という意見が発生するかというと、多分そこまで強い権限を持ってるのって、出資者じゃなくて大手の配給会社だと思う。
「ここをこう変えてくれ」「主役がこれくらいの格の人が来れば、うちで配給ができますよ」みたいなことだと思うんですね。だから実は予算の大小で、「大きいから大変だ」「小さいから簡単だ」ってことは一概には言えないんです。

── 製作過程においては予算が影響するとは限らないんですね。では企画を決める過程において、高予算ならではの構造はありますか?
それはあると思います。うちの場合は親会社が「木下グループ」という大きい企業ですけど、考え方が独立系なので「大きい予算を引き出したいからこういう企画をやる」とか、「こういう内容であれば当たるって思われるだろうから」とはならないんです。
でも他社の行動を見ていると、大きい会社であればあるほど、売れてる原作モノの企画になる。テレビ局もそうですよね。よく駅とかで小説の広告を見ますけど、10万部突破、20万部突破って文字を見ると「どこかが映画化するだろうな」って思うし、どこが手を挙げるのかなって思っていたら大手だった、っていう。
やっぱり売れてるものとか、普段から目に触れることが多いものは、知ってもらう努力をしなくてもみんな知ってる。それだけの人が知ってるものと、まったく知られていないもの、たとえば、うちが製作したオリジナルの『半世界』(2019年)という映画だと、スタートダッシュが全然違う。大きなハンデがある。だったらハンデがないほうがいいって普通の人は考えるじゃないですか。だから、やっぱり売れてるラノベっぽいものとかが多い。
「あれを文学と呼んでいいのか」とかいろんなことを言う人がいると思うんですけど、映画会社からすれば当たればいいし、若い子がいっぱい読んでる本なんだから、「これは小説じゃない」とか「文芸じゃない」とか、どうだっていいことだと思うんですよ。

── 原作モノの作品と、『半世界』のような骨太なオリジナル作品とだと、前者はすぐに消え、後者はずっと残っていくように感じます。長い目で見たときに、原作モノの作品の価値についてはどうお考えですか?
価値というよりも、そもそも消費されるスパンが短くなっているので……。昔はロングランを平気でやっていた。何十週って。いまそれができなくなってきている。どっかで切られちゃうんです。あとDVDがだんだん売れなくなってきているから……昔はジブリの映画なんて、公開してから1年経たないとビデオにならなかった。
大手も公開してから6カ月以上。それがいまや、洋画メジャーなら公開されてから4カ月後3カ月後にDVDが出るようになり、ユーザーもそれを知っちゃってる。「観に行けなかった。でもいいや、すぐDVD出るから」ってなってしまっていると思います。

予算を回収するサイクルが変化し、形になる企画も変化
── 最近はレンタル店から棚落ちするスピードも早いんですか?
1年で消えますよ、よっぽどの作品じゃないと。棚に限りがあるので。往年の名作と呼ばれるもの、これ置いとかなきゃっていうもの以外は全部はけていかないと。どんどん増やせるわけじゃないので、売り場面積って。その上、さらにSVOD(定額制動画配信サービス)もやってきて、わざわざレンタル店に行かなくても、たとえば月額980円払えば見放題、とか。
だから、いままでは劇場で観られる期間があって、その半年後にビデオやDVDっていうので1本の作品を3年くらいで回収してたんですが、いまは1年ちょっとに縮まってきてる。で、どんどん作品が量産される。出演している人も、なんとなく似ている。だから覚えられないし、私なんかは観たいとも思わない。
でも多分いまの若い子たちは、この瞬間最大風速が吹いて話題になってるものを観ておかないと取り残されてしまう恐怖心と戦ってるから、私なんかが青春を過ごしていた時代とは全然違うプロセスを経て、いまという時代を生きてる。だからそういう子たちには、そういう映画は合っていると思います。

── いまのニーズには合っているということでしょうか?
そうですね。ただやっぱり興行成績を客観的に見た場合、かつてだったら30億いったよねという作品が、いかない。10億も超えなくなってる。だから大手各社は、わかりやすくそういうちょっとキラキラした映画を減らしてきてるなと思いますよ。
若い子たちも流行には飛びつくけど、選球眼は持ってるから、少ないお金を何にでもは払わない。作品が量産されて、選択肢が多くなればなるほど、それがバラけもするじゃないですか。そういうところは、きっと大手さんも調整されてるんだろうなと。そういう意味で言うと、コンテンツ自体が消費される期間が短くなってるけど、「短くなってもしょうがない」ってつくってるほうも気づいてると思いますよ。
だから私は、ヒットした感じがなかったとしても、観た人が「いい映画だったなあ」とか「あのシーンがいいんだよ」とかって何カ月か経ったあとでも思い出せる映画のほうが、お金にならなかったとしても、人の記憶に残っていくっていう価値が出せるのかなって思います。

── 時代とともに形になる作品も変わってきているのですか?
実感値としては、ビデオが数字にならなくなってきたので……昔は出せばお金になった。それをあてにして、インディペンデントの人も映画をいっぱいつくれた。でもいまレンタル店が衰退してきたから、劇場である程度稼がなきゃいけない。
自社グループで劇場を持っている大手配給会社は、高予算でも回収できる可能性がある。でも私たちは難しい。となるといかに安くつくるかにシフトする。でも、いくらでつくったかなんてお客さんはわからないじゃないですか。だから値ごろ感があるようにしながら。
うちがつくった『台風家族』もいくらでつくられているのかお客さんはわからない。あれだけのキャストがそろえば「なんかおもしろそう」って思ってもらえるだろうと。『台風家族』を2億かけてつくることもできるけど、2億かけるってことは宣伝費も考えると興行収入で5億円以上いかなきゃいけない。5億以上いかなきゃいけないってなると、何館で1日何回上映して、それを何週やらなきゃっていう簡単な足し算かけ算になっていくんですね。
さらにいまは、アニメも強いから。もともと子どもだけが観るものだったんですけど。コナンを観て育った子どもが大人になって、自分の子どもといっしょに観に行くようになって、70億80億いくようになった。ドラえもんでも同じ状況になってますよね。
── 結構なスパンでやってますよね。
たとえばポケモンは、毎年夏休みに上映しますよね。子どもが休みのときに、いかに稼ぐかってことを大きい会社さんたちは考えてブッキングする。
そうするとこちらは夏にブッキングが取れない。というような状況があるなかでやってかなきゃいけないから、やっぱり安くつくる作品も増えてくる。その最たるものが『カメラを止めるな!』。
でも、あれは簡単に二匹目のどじょうは釣れないとも思ってる。自主映画のようなものだからあの金額でできるけど、あれを本当にスタッフとキャストを集めてつくったら、みんなポケットマネーを出してやるしかないから商業映画になり得ない。そこがすごく難しい。

原作モノ主義により、日本は遅れをとっている
── 過去のインタビューで、キノフィルムズは多様性や作家性を重視するというお話を拝読しました。やはり原作モノ志向に対するアンチテーゼがあるのでしょうか?
ある。洋画の買い付けをやっていたときに、海外の映画祭にいっぱい行ったんですよ。オリジナルの映画がなんと多いこと! そしてとってもおもしろいんです。海外の映画祭に、日本の映画が出ていけないのはそこだと思っています。多分コンテンツの価値というところで、日本は1億3,000万人くらい人口がいるから、ヒットすれば国内だけで確実に回収できるんですよね。だから日本は、海外から回収することが必須条件ではないんです。
ただやっぱり韓国映画やK-POPが強いのって、韓国は人口5,000万人くらいしかいないわけですから、彼らは外貨を稼がないと儲けられないとわかってる。だから徹底したエンタテインメントでアメリカに出て、男性のグループも女性のグループも1位をとってしまう時代になってるっていうのが、映画でも同じことが起きていると思っていて。経済的には日本のほうが総じて上かもしれないけど、文化度でいうと日本はものすごく遅れをとってる。
だから海外の映画祭に行くと悔しいんです。なんでこういう映画を日本でつくれないんだろ? って。もちろんそういう映画だと、日本では勝率は下がるんです。知らないものを出さなきゃいけないから。でも知られてなかったとしても、その監督に才能があるとこっちが思って、その人とつくったお話を誰かに届けたいと思って、国内だけじゃなく世界の人にも通じる人にしたいなと思ってやれば、どうにか突破口が開けるんじゃないかなと思ってます。
うちのボス(木下直哉会長)は、それを認めてくれる希有な人なんです。それは映画だけを生業にしてるわけじゃないから言えることだと思うんですよね。映画だけで食べてる人たちは「儲けてなんぼだろ。客が入る企画出せ」って言うと思うんですよ。となるといきなりオリジナルはないだろうし、オリジナルでやれる人も限られて「名監督ならよしとする。でも必ずテレビ局と組むこととする」とか。その証拠にだんだん名のある監督でさえ、オリジナルで撮れなくなってきてると感じます。おもしろくても、オリジナルってつくりづらくなってるんです。

── このままだとどんどん名作が減り、観客の観る目も劣化していくのでしょうか?
そうさせないためにも、本当におもしろい映画をつくり続けなきゃいけないし、そういう洋画を知り続けなきゃいけないっていうのがうちのボスが思ってることで。いまはハリウッドも同じで、当たるとわかったらそのシリーズばっかり。ヒーローが一同に会して悪と戦う、みたいな。それが黒人だったり白人だったり、緑の人だったり神様だったりするだけで。
最近、自分が洋画を観なくなっちゃったのはそこだなあと。映画が大好きでこの業界に入ったのに一番観てない、マーベルシリーズを。もちろんおもしろいものもあるんですけど、そういう風潮をハリウッドもつくり出しちゃってるってのは感じる。ただハリウッドメジャーが捨てたもんじゃないなって思うのは、一方で作家性の強い監督を囲って、オスカーの候補になるような作品をつくり始めていること。
あれはすごい。でもそれをメジャースタジオにやられると、インディペンデントの人が困りますよね。メジャースタジオとインディペンデントの色分けがなくなってしまうから。そうすると、映画をつくりたいけどお金はない、っていう才能ある製作者たちはみんなメジャースタジオに流れちゃう。インディーズの人たちがつくりづらくなる。
全世界的にも、大規模な映画か、ミニマムにつくるかに二分されてしまっている。中規模のものは非常につくりづらい。日本国内もそう。以前よくつくられていた、1億〜1億3,000万くらいの作品が非常に回収しづらくて。規模も中途半端になっちゃうし。だとすれば250〜300館開けられるものにしないと。それができるのが原作モノとか、超有名な人が出てるものとか。オリジナルだとしても、「これは感動しそう」って観る人に一発で伝わるものでないといけない。
ベストセラーのような原作モノは否定しないですけど、でもオリジナリティのあるものってまだまだつくれると思うし、それがキノフィルムズの色になっていけばいいと思う。それがうまくいってくると、「ぜひ読んでみてください」ってオリジナルの脚本を持ち込んでくれる製作者が増えてくると思ってて。全部が全部はできないですけど、対話しながら、こういうカタチだったらできるよと。いま準備してる作品も、ほとんどがオリジナルなんです。
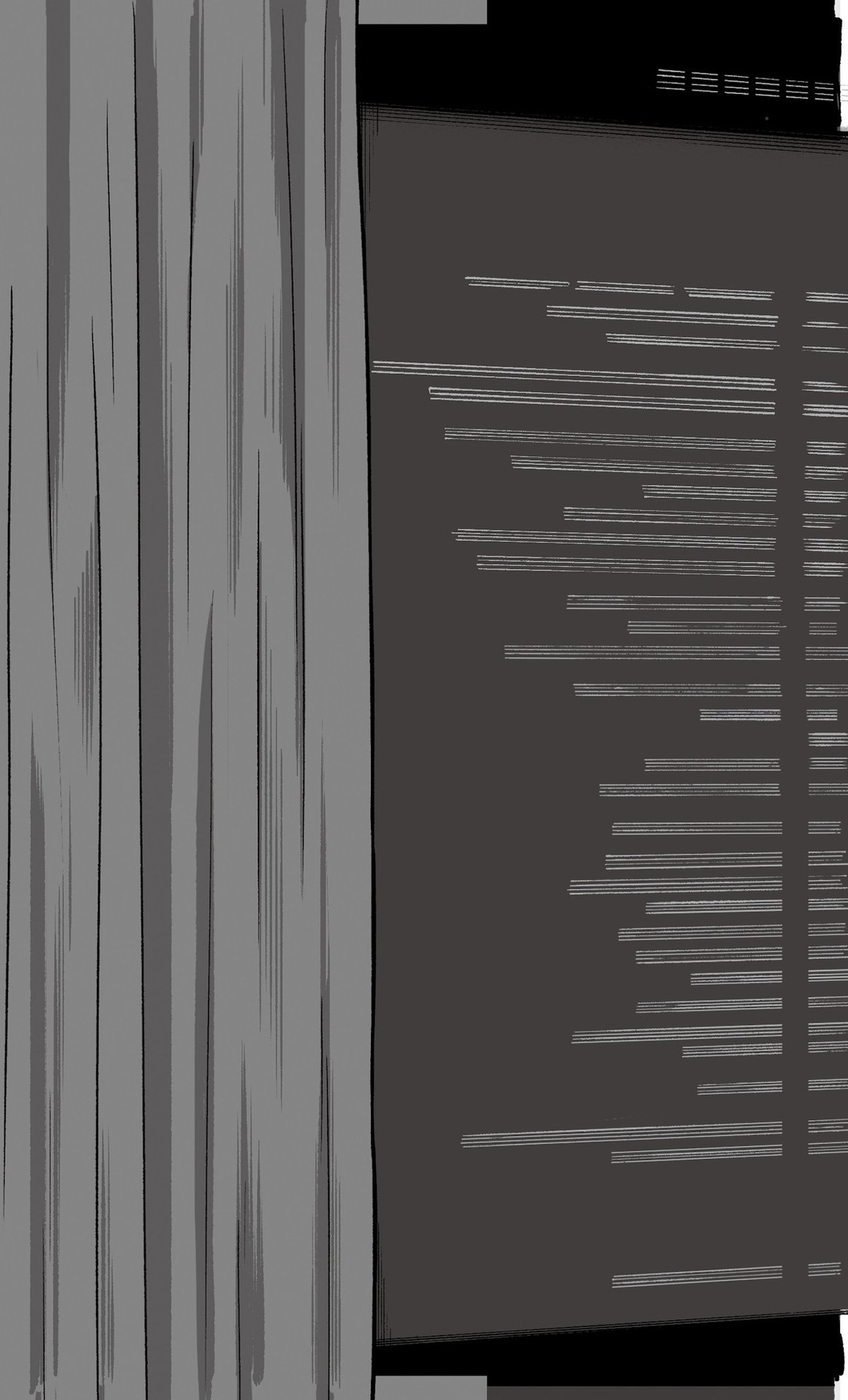
── こんな時代だからこそ、作家性主義なんですね。
もちろん。ただ作家性主義や多様性は大事にしつつも、それを大声で言ってるだけでは負け犬の遠吠えになるので、結果を出したい。誰も観ないものを、自分たちの軒先に並べて「すげえだろ」っていうのは違うので。だから届ける意味があるもの、「これは!」っていうものはやりたいし、今期はそういう映画が多い。「みんなに観てほしい!」っていう作品が結構あるので、そういうものは燃えるし、絶対観たら人の心に爪痕を残すし、これ観たあとに緩い映画を観たら腹が立つ、みたいな。やっぱそういう作品が世界にはいっぱいあるから。
聞き手・文:吹上 洋佑/イラスト:サヌキ ナオヤ
武部 由実子 (たけべ ゆみこ)
ギャガ宣伝部を経て2004年より映画製作に従事。2009年よりキノフィルムズにて製作プロデューサーと配給統括を兼務。主なプロデュース作品に、星野源主演『箱入り息子の恋』(2013年)、松尾スズキ監督『ジヌよさらば~かむろば村へ~』(2015年)、阪本順治監督『団地』(2016年)、河瀨直美監督『光』(2017年)などがある。
_______________
この記事は2019年7月24日に発売された雑誌『広告』リニューアル創刊号から転載しています。
いいなと思ったら応援しよう!

