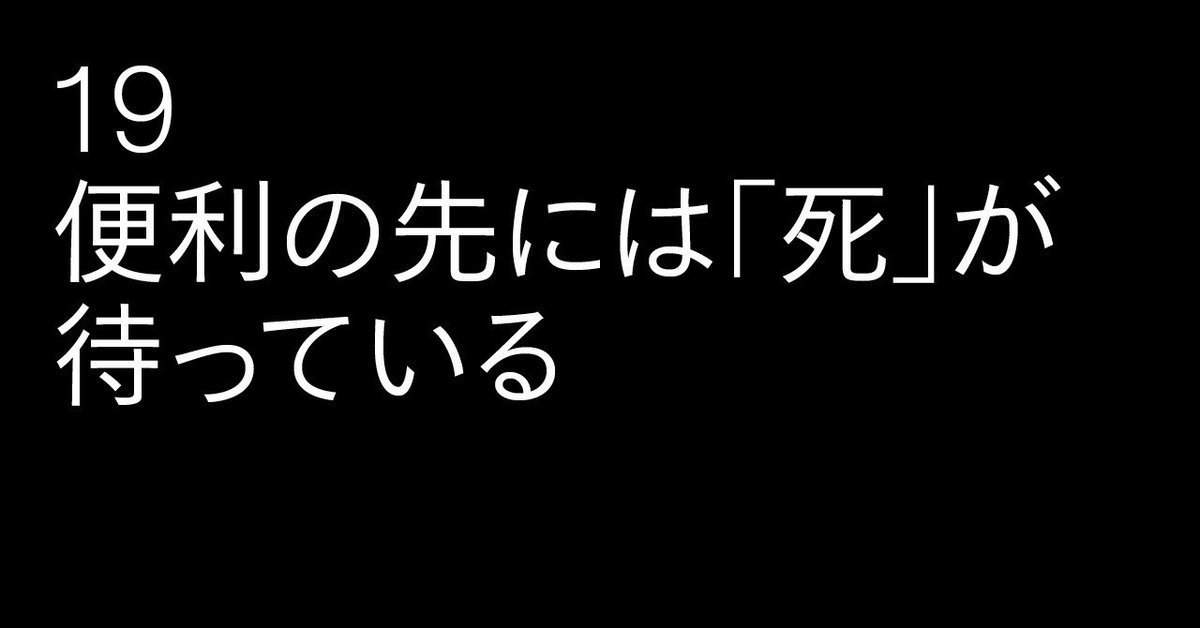
19 便利の先には「死」が待って いる
私たちは便利さを追い求めて、身体に代わって労働をしてくれる道具を生み出し続けてきた。いまでは、家事は電化製品を使用すればいいし、それも面倒なら外のサービスを利用すればいい。そんな暮らしは、とても気楽で快適だ。でも、そのような発展のしかたをこれからも続けていって、本当に大丈夫なのだろうか? 便利さを追い求め切り捨ててきたもののなかに、失ってはいけないものがあったのではないだろうか?
「負荷がない=豊か」という幻想
チンパンジーが枝を使ってアリの巣をまさぐるように、きっと人類の祖先たちも手近な枝や石を拾って「道具」として使用したのだろう。人の手によって加工された道具が登場するのは約260万年前のこと。「オルドワン石器」というもので、動物の死骸から肉を剥ぎ取り、骨を割って栄養豊富な脊髄を取り出すことなどに使用されたと考えられている。人は道具を生み出すことで、手足だけではできなかったことを可能にした。
人と道具の関係について考察する上で重要な人物に、カナダの批評家マーシャル・マクルーハン(1911〜1980年)がいる。彼は、道具をはじめとしたあらゆる人工物は、人間の身体および精神の拡張物であると主張した(※1)。
たとえば、自転車は私たちの足を拡張させたものだし、ナイフは歯を拡張させたものだ。衣服は皮膚を拡張させたものだし、メガネは目を拡張させたものだと言える。でも、「車は足を拡張させたもの」と言われると、なんだかピンとこない。車と私たちの身体はあまりにも隔たりがあるように感じてしまう。……自転車は足で漕ぐぶんだけ身体に負荷がかかるけれど、車は身体への負荷が少ないことがその理由なのだろう。
道具の進化にはいくつかのレベルがある。オルドワン石器は間違いなく身体の拡張物だった。しかし、18世紀の産業革命の頃に、道具と人との関係が大きく変化する。動力を持つ機械が生まれ、身体のエネルギーを使わなくても「行為」を行なうことが可能となった。
いまでは、ボタンひとつで機械が労働を行なってくれるため、道具は身体の拡張物であるとする感覚が薄れ、身体と切り離された「外部装置」へ移行している。身体にかかる「負荷」は取り除かれるべき無駄なものだと考えられ、便利な外部装置を増やして負荷の少ない人工環境を築くことが、豊かな社会のありかただと私たちは信じている。

私たちは、生きながら死にかけている
外部装置が増えて生活が便利になったことで、何をするにしても負荷が少なくなり、人の身体活動量は大幅に減っている。なおかつデスクワークが増えていて、肥満や腰痛、生活習慣病……様々な不調を抱える人が多い。身体活動量の減少によって引き起こされる不調をいくつかあげてみよう。
①廃用症候群
加齢や疾病、障害などによって体力が落ちている人が極端に活動量を減らすと、筋肉や内臓、脳の機能が低下して、「廃用症候群」という状態に陥る。廃用症候群によって、肺炎を起こして死んでしまうことすらある。
②うつなどの精神疾患
2017年に米医学誌『The American Journal of Psychiatry』で発表された研究によると、運動がうつ病などの予防に役立つ。長時間座ったまま過ごす生活は、うつ病の発症率を高める。
③記憶力の低下
2015年に米医学誌『JAMA Psychiatry』で発表された研究によると、「1日に長時間テレビを視聴する習慣があり、運動習慣がない人」は、そうでない人と比べて記憶力が大幅に落ちてしまう。さらに、2016年には米医学誌『Neurology』で、中年成人の運動不足が脳の老化を早めているという研究が報告されている。
生きるためには身体を動かすことが不可欠で、負荷がなくなってしまうと肉体と精神は劣化してしまう。便利さを求めて文明を発展させてきたつもりが、気づいたときには「死」に近づいてしまっているのだ。そうした認識のもと、生活のなかにある負荷を大切にする医療介護施設も登場している。
山口県を中心に展開されているリハビリ施設「夢のみずうみ村」はそのひとつだ。施設内に、あえて段差や階段などの「バリア」を配置することで、利用者の身体回復を図る「バリアアリー」という試みを行なっている。ほかにも、大阪府にあるグループホーム「むつみ庵」は、建物に古民家を利用する。
あえて急な階段や敷居を残すことで、認知症の進行をゆるやかにさせて、自立的な生活を維持させている。多くの医療介護施設ではセンサー付きの蛇口が採用されていて、そのせいで認知症者や高齢者が蛇口のひねりかたすら忘れてしまうことも多い。古民家を利用するむつみ庵では、そうした能力の低下も防ぐことができる。

道具の奴隷となった私たちはどこへ向かうのか?
肉体と精神を不調から回復させるためには、身体を動かせばよい。しかし、それだけで外部装置化の問題がすべて解決するわけではない。外部装置化によるいちばんの問題は、これまで自らの手で行なっていた行為を外部へ委託するようになるために、人間の自立性が奪われてしまうことだ。
移動が、足から車、さらには電車や航空機に変化したように、道具は外部装置になり、さらには操作する必要がない「サービス」に置き換わった。いまでは、サービスが供給してくれる「もの」を頼って私たちは生活する。でも、サービスは意外と脆弱であることを、私たちはすでに知っている。
ひとたび災害が起きれば、電車は止まってしまうし、昔の人のように自ら道具を用いて食料や水を確保しているわけではないから、それも難しくなってしまう。……そのとき、丸腰で荒野に放り出されていることに、私たちはやっと気がつくのだろう。
さらに、外部装置化した道具やサービスに依存することで主体性すらも失われてしまう。合理化が進んだ工場では、ベルトコンベアに合わせて作業員の行動範囲や作業工程、行動時間などが細かく決められているが、それはまるで道具に支配されているようだ。同じようなことが社会全体で起こっているのかもしれない。電車や航空機の都合に合わせて行動することを当然だと思っているし、カーナビに従って運転をしていたら海へ落ちた、という事例も実際にある。
思考を停止させて人工環境に生きる人間のことを、動物学者の小原秀雄(1927年~)は「自己家畜化」(※2)という痛烈な言葉を用いて批判した。自己家畜化した人間は、自立性と主体性を奪われて、尊厳としての「死」に陥っているのだ。

いま私たちが追い求めるべき道具とは?
オーストリアの思想家イヴァン・イリイチ(1926〜2002年)は、「人々は自分のかわりに働いてくれる道具ではなく、自分とともに働いてくれる新しい道具を必要としている」と主張した(※3)。彼は行き過ぎた産業主義によって生み出された道具が人の能力を奪い、人が与えられたものをただ受け取るだけの「消費者」になってしまっていることに対して警鐘を鳴らした。
大きな産業によって生み出された道具に対する抵抗は、イリイチ以前にも行なわれている。19世紀末から20世紀初頭には、ウィリアム・モリス(1834~1896年)によって呼びかけられた「アーツ・アンド・クラフツ運動」が展開され、20世紀前半には、柳宗悦(1889~1961年)が「民藝運動」を展開した。
彼らの運動は、産業革命によって大量生産された道具を批判し、人の手によってつくられた道具が持つ美を見出すことだった。それは、道具を自らの身体に取り戻そう(身体の拡張物としての道具へ引き戻そう)とする試みだったとも言えるだろう。1968年には、ステュアート・ブランド(1938年~)が雑誌『ホール・アース・カタログ』を創刊。
彼は、“本当に”役立つ道具とその入手方法を紹介することで、消費者として生きるのではなく、自立的な生活を築くことを提案した。日本では、2011年を境にコミュニティや経済、暮らしかたを見直す人々が増えて、「小商い」や「DIY」といったテーマが考え直されたことは記憶に新しい。

20世紀後半にはコンピューターによる機械の自動化が進み、昨今ではAI(人工知能)の導入により道具は新たな局面を迎えている。自立的な思考を可能にするAIの登場で、人間の思考すら道具が代替してくれるようになった。
インターネット上の広告やECサイトでは閲覧や購入履歴にもとづいて「もの」が表示され、AI技術の向上によりそれはますます最適化されるだろう。近い将来、私たちは自分の思考によって「もの」を選び取る必要すらなくなるのかもしれない。
自立的に動く道具の登場により、「道具は身体の拡張物」という感覚はついに消え去ろうとしている。これまで、労働を代替してくれる外部装置を便利だとありがたがって、際限なく増やし続けてきた。
でも、その方法によって肉体と精神は不調をきたし、自立性と主体性は失われて、人は死に近づいている。過ぎた時代に戻ることはできないし、時代回帰を主張することは後ろ向きすぎる。それでも、私たちは生活のなかで身体を主体的に動かし続けることでしか、「生」をまっとうすることはできないはずだ。

イリイチは、人間が道具に奴隷化されない範囲を自らが理解して、道具の活用に制限を与えることが必要だと訴えた。そして、人が本来持つエネルギーを使う道具のことを「コンヴィヴィアリティ(自立共生)のための道具」と呼んだ。いま、彼が示した道具への模索が求められている。その糸口は、これまで無駄だと切り捨てられてきた負荷を取り戻すことにあるはずだ。
文:東江 夏海/写真:青木 柊野
東江 夏海 (あがりえ なつみ)
編集者、ライター。出版・編集プロダクション「デコ」に所属し、雑誌や書籍、小冊子、ウェブ媒体などで編集・執筆を行なう。医療や社会福祉のテーマを得意とし、医療健康フリーマガジン「からころ」などを担当。最近、編集した書籍に『脳を傷つけない子育て』(河出書房新社)がある。
脚注
※1 道具をはじめとしたあらゆる人工物……マクルーハンが言う人工物には、道具のほかに、言語、法律、思想、仮説、衣服、コンピューターなどがあげられている。
※2 自己家畜化……「自己家畜化」という考えかたは、E・フォン・アイクシュテットにより初めて提唱された。
※3 「人々は自分のかわりに働いてくれる道具ではなく〜」……イリイチが言う「道具」のなかには、ナイフなどの道具はもちろん、機械や教育、医療などのあらゆる制度も含まれている。
参考文献
『サピエンス異変―新たな時代「人新世」の衝撃』(ヴァイバー・クリガン=リード、飛鳥新社、2018年)/『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(更科功、NHK出版、2018年)/『メディアの法則』(マーシャル・マクルーハン、エリック・マクルーハン、NTT出版、2002年)/『ペット化する現代人―自己家畜化論から』(小原秀雄、羽仁進、日本放送出版協会、1995年)/『コンヴィヴィアリティのための道具』(イヴァン・イリイチ、ちくま学芸文庫、2015年)/『家庭医学館(ウェブ版)』(小学館)/Samuel B. Harvey , F.R.A.N.Z.C.P., Ph.D., Simon Øverland, Ph.D., Stephani L. Hatch, Ph.D., Simon Wessely, F.R.C.Psych., M.D., Arnstein Mykletun, Ph.D., Matthew Hotopf, F.R.C.Psych., Ph.D,(2017)「Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study」『The American Journal of Psychiatry』/Tina D. Hoang, MSPH; Jared Reis, PhD; Na Zhu, MD, MPH; David R. Jacobs Jr, PhD; Lenore J. Launer, PhD; Rachel A. Whitmer, PhD; Stephen Sidney, MD; Kristine Yaffe, MD,(2015)「Effect of Early Adult Patterns of Physical Activity and Television Viewing on Midlife Cognitive Function」『JAMA Psychiatry』/Nicole L. Spartano, PhD,corresponding author Jayandra J. Himali, PhD, Alexa S. Beiser, PhD, Gregory D. Lewis, MD, Charles DeCarli, MD, Ramachandran S. Vasan, MD, and Sudha Seshadri, MD,(2016)「Midlife exercise blood pressure, heart rate, and fitness relate to brain volume 2 decades later」『Neurology』
_______________
この記事は2019年7月24日に発売された雑誌『広告』リニューアル創刊号から転載しています。
いいなと思ったら応援しよう!

