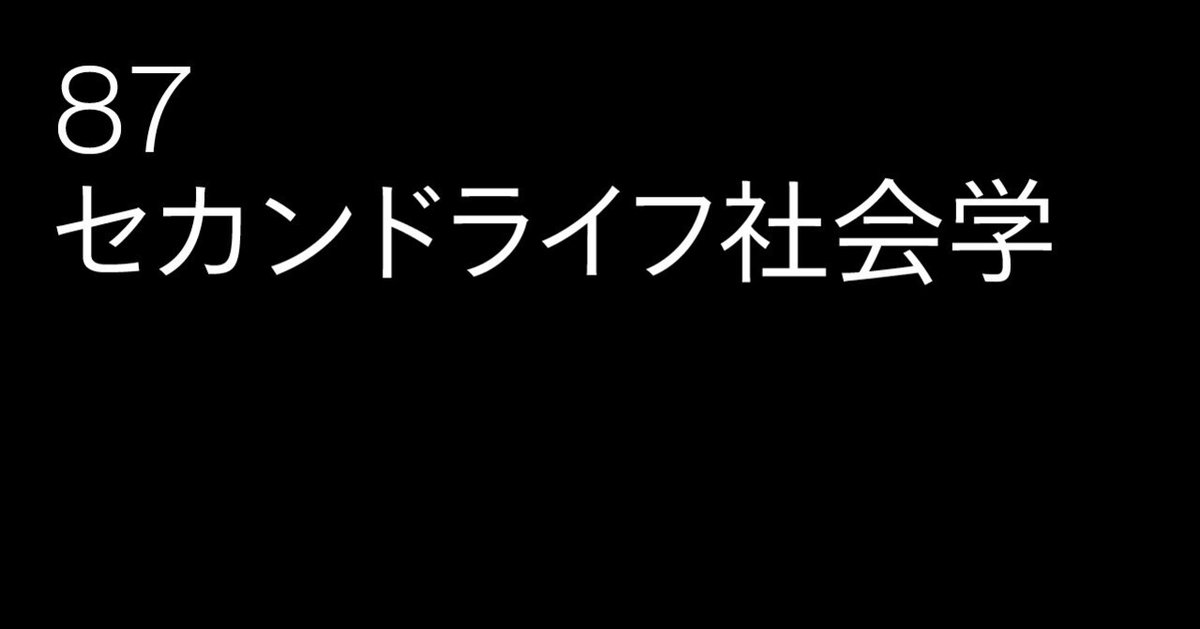
87 セカンドライフ社会学 〜 社会学者 池上英子 インタビュー
1992年、SF作家のニール・スティーヴンスンは『スノウ・クラッシュ』にて、「メタバース」という言葉を発明した。作品内に登場する架空の仮想空間を「メタバース」と呼び、それから約30年が経ったいま、この言葉は再び注目を集めている。
たとえば、フェイスブックは2021年10月に「メタ(Meta)」へと社名変更を発表し、「メタバース」の構築に乗り出してきた。またフィクションの世界で言えば、『スノウ・クラッシュ』以降も『レディ・プレイヤー1』や『マトリックス』、日本では『ソードアート・オンライン』といった作品が、人々のメタバース観をかたちづくってきた。
そうした「メタバース」や仮想空間を考えるうえでいまこそ参照されるべきサービスのひとつが、2003年に始まった「セカンドライフ(Second Life)」だろう。
その名のとおり「もうひとつの人生を生きる」ための広大な空間として国内外の様々な企業がセカンドライフに参入し、盛り上がりを見せた。ゲーム内通貨である「リンデンドル」は現金(米ドル)に換金できたため、セカンドライフの土地売買でリンデンドルを稼ぎ、米ドル換算で100万ドル以上を手に入れたユーザーが出現したことも話題となった(※1)。
セカンドライフは、『フォートナイト(Fortnite)』や『ロブロックス(Roblox)』といった昨今のゲームを起点としたメタバースとは異なり、所与のゲームシナリオもなければ、何かを競うわけでもない。家や街並み、アバターも自分でデザインできる。普通のゲームとは異なるため、ゲームに慣れた人は何をしてよいのかわからず戸惑ってしまう。
また、当時セカンドライフの世界にジャックインするためのPCの必要スペックが高かったことや、同時接続人数の少なさなどを理由に人気は下がっていった。バーチャルSNS「クラスター(cluster)」CEOの加藤直人氏は、セカンドライフ失敗の最大の理由は「過疎りやすい構造」だと分析する。「セカンドライフではひとつのワールド(「シム」と呼ばれている)に最大50人しか入れませんでした。さらに、ユーザーが自由に空間をつくれたので(アバターの)密度が低くなりがちだったのです」
しかし、セカンドライフを開発したリンデンラボは現在もサービス運営を続けており、日本経済新聞の記事によれば2020年時点で月1回以上利用しているユーザーは75万~90万人いるという。また現CEOのエッベ・アルトバーグ氏は「2007年のブームは時期尚早で過剰だった。セカンドライフが本当に盛り上がるのは2027年だろう」と発言している(※2)。
かつてセカンドライフの創業者であるフィリップ・ローズデールにインタビューしたとき、「セカンドライフはアバターとテキストだけの世界でしたが、非常に強力な空間でした。人々はそこで恋に落ち、結婚し、いっしょにビジネスをしました」と当時を振り返っていた(彼はいまセカンドライフの運営からは離れているが、彼の新会社ハイ・フィデリティのオフィスを訪ねたときに見た、壁に飾られていたセカンドライフの最初のサーバーが印象的だった)。
今後、もし現行のメタバースが拡大していくとすれば、セカンドライフから学べることは何だろうか? 仮想空間に立ち現れた「社会」とはいかなるものだったのだろう? そのヒントを探るために、ある研究者にインタビューを依頼した。ニュー・スクール大学大学院社会学部教授の池上英子氏だ。
池上氏はセカンドライフ内に自らの研究所「ラ・サクラ(La Sakura)」をつくり、仮想空間のユーザーをエスノグラフィ調査するなかで、とくに自閉症スペクトラムの人々と仮想空間で交流を深め、『ハイパーワールド──共感しあう自閉症アバターたち』(NTT出版)や『自閉症という知性』(NHK出版)などの書籍にその研究成果をまとめてきた。セカンドライフという仮想空間を社会学的な眼差しから研究してきた池上氏が、その空間の特異性を存分に語ってくれた。
複数のアイデンティティを行き来する
── 今日は「メタバース社会学」を大きなテーマとして、セカンドライフのなかでデジタルエスノグラフィーを行なってきた池上先生にお話を伺えればと考えています。先生は、セカンドライフにおいては「キレミミ・タイガーポウ」というハンドルネームで活動されていたのだとか。
池上:そこから聞きますか(笑)。深い意味はないのですが、ちょうどその頃は沖縄の八重山諸島を旅したあとで、たまたま石垣島の店で購入した文庫本に出てきた気が強くてエレガントなイリオモテヤマネコ「キレミミ」の名前を借りたんです。米国での生活で、私は喧嘩の語彙が未発達だったせいか、おとなしくて優しい東洋人だと思われがちだったので、そのメス山猫にあやかりたいという気持ちがあったんです。

右端の人物が池上氏のアバター「キレミミ・タイガーポウ」 画像:池上英子氏提供
── 現実とは少し異なる、気が強い自己になるための命名だったんですね。
池上:そうですね。「アバター」という代理の自分の身体を持ち、仮想の環境や社会のなかで第二、第三の、ときにはそれ以上のアイデンティティを育てるとはどういうことなのかに興味があったんです。だからこそ、現実の自分とは異なるアバターにしてみたんですよね。
デジタル世界のアバターは自分の分身であるものの、仮想世界のほかの住人の言葉や行動に触発され、ときに自分でも思いがけない行動をとったり、普段とは異なる自分を発見したりすることがあります。自分がアバターを使うのではなく、アバター自身が新しい生命を持つかのように、新しいアイデンティティを獲得する状況になっていくんです。
最後までお読みいただきありがとうございます。Twitterにて最新情報つぶやいてます。雑誌『広告』@kohkoku_jp

