
やさしい革命4 オープンになろう (永井元編集長イチオシ記事 #5)
他者との「壁」をコントロールできる未来へ
一口に「オープン」といっても、別にすべてをオープンにしようというのではない。誰もがTwitterやFacebookでプライバシーをさらけだす必要はないし、TPPのようなグローバリズム礼賛というわけでもない。大切なのはバランスだ。ただ、ある部分をオープンにすることで、自由やつながり、シェアやイノベーションが生まれたりする。
では、何をどれくらいオープンにすればいいのか? そこから生まれる未来とは? 4つの面から考えてみた。
同質性と多様性の間で
「同質性が高い」といわれてきた日本社会。そこでは「あうんの呼吸」が通じる心地よさもあるし、治安のよさもある。大量生産方式やマスメディアには効率的で都合がよかったし、スムーズに動く社会やチームで一丸となる力は、戦後日本の高度成長を支えてきた一因でもある。
一方で、外部との間に「壁」が生まれてしまい、異質なマイノリティーを排除する傾向も強い。壁の内部には「同調圧力」がはたらくので、「空気を読まない」人は疎まれ、「出る杭は打たれる」。ネットでの「炎上」やいじめ、人種差別をはじめ、原発をめぐる隠蔽性、企業の隠蔽体質など、同質性による「閉鎖性」を挙げだせばきりがないだろう。
生物学の世界では「多様性をもたない生態系は硬直的で脆く崩壊しやすい」といわれるが、それは人間社会でも同じだ。日本社会の「同質性」のよさを残しつつ、いかに「多様性」を確保するのか。そのために、他者との間の「壁」をどう調節していくかは、これからの大切なテーマだといえる。

『全人類対話場 A dialogue place for all mankind』(2012年春着工予定)。「全ての人類に、開かれた対話の出来る場所」をコンセプトにアーティスト、新野圭二郎が構想中の作品。周囲の自然の変化を反映する水鏡の上に並ぶ、誰も座っていない椅子がそこから生まれる対話を待ち続ける。
オープン・マインド
オープン&シェアを本質とするインターネットやソーシャルメディアが普及した今、人々は自分の趣味や嗜好に応じて知識を深め、リアル・バーチャル問わず簡単にコミュニティを形成できるようになっている。しかし、それでも細分化した同質のコミュニティ内で自閉し、いわゆる「専門バカ」や異質な他者を排斥する「小さな鎖国」が乱立する危険性をはらんでいる。多様な人やコミュニティが互いに孤立せず、ゆるやかにつながっていくにはどうすればいいのだろうか?
重要なのは、少数の異質な意見や価値観を差別せずに認める「寛容性」だ。それは「みんなが同じ」ではなく、「みんなが違う」ことを前提に互いに認め合うオープンマインド。たとえば、まったく異質な意見や行動を耳にしたときに、あなたならどう答えるだろう? 「意味わかんない! あり得ない」と答えるとしたら不寛容、「へぇー」ボタンを押すくらいが寛容性アリといえるかもしれない。そんなオープンで包容力のある社会でこそ、誰もが同調圧力から解放されて自由になり、その能力をフルに生かすことができるようになる。
近年では企業の経営戦略でも「ダイバーシティ・マネジメント」(注1)と言われるように、多様性に寛容な社会は「創発」を生み、新たな「創造」にもつながる。「クリエイティブクラス」(注2)を提唱するリチャード・フロリダは経済発展に必要な条件としてタレント、テクノロジー、トレランス(寛容性)という3つのTを挙げ、特に3つめのTを必要不可欠なものとしている。単に異質な人を受け入れるというだけでなく、標準から外れたアイデアや情報に寛容な社会こそがイノベーションをもたらし、経済を繁栄させる。
もちろん、個人が個人として存在する以上、他者との間にある程度の「壁」は必要だ。けれど、その壁を少し下ろして風通しを良くすることで、誰もが自由になり、多様な力のコラボレーションが社会に活力を生む。
いわば、オープンマインドとは「未知のものへの寛容性」であり、「変化への柔軟性」だ。それは異質な他者との間によけいな「壁」をつくらず、一緒に未来をつくりあげていく「開かれた態度」なのだ。
注1 【ダイバーシティ・マネジメント】
個人や集団間に存在するさまざまな違いを認め、多様性を競争優位の源泉として生かすために文化や制度、プログラムプラクティスなどの組織全体を変革しようとする経営戦略。
注2 『クリエイティブクラスの世紀』
リチャード・フロリダ著 ダイヤモンド社(2007)
オープン・バウンダリー
「壁をつくらない」ということは、そのまま建築にも通ずる。というより、隈研吾監修の『境界』(注3)によれば、それはル・コルビジェやフランク・ロイド・ライトといった20世紀初頭の建築家たちがやろうとしたことそのものである。彼らはそろって壁を捨て、ガラスと鉄による「透明性」を意識した建築を設計してきた。そんななかで、内部と外部の境界をオープンにすることにもっとも意識的だったのがライトであり、そのヒントとなったのが日本の伝統建築だったという。ライトは、万国博で平等院鳳凰堂を模した「大屋根が作る大きな影の中の、壁のない透明な建築」に決定的に影響され、乱暴なまでに壁を壊しオープン化を押し進めた。
しかし、外部に完全にオープンな空間は、そこに住むやわな人間にとっては快適とはいえない。現代の日本建築はそんな反省から、外部と内部の境界をつくる技術を人間に合わせて洗練させ、進化させてきたものだといえる。隈研吾による根津美術館は、周囲の都市に対して閉じるのではなく、竹林によって外部にゆるやかに開かれている。藤本壮介氏のHouse Nは「ぼんやりとした境界」を建築にしたものだ。それらは襖や障子で区切られた空間でとなりの気配が感じられたり、縁側に近所の人が気軽に出入りできたように、「内と外の曖昧な境界」によって周囲の自然や人との豊かな関係をつくっていた日本の伝統的空間観につながっている。
そうした境界を曖昧にする考え方は、『まちの保育園』(注4)にも見られる。開放感のある園舎や園庭、開園当時は敷居もなかったというこの保育園では、カフェを併設することで、保育士や保護者だけでなく、地域の人が園の教育や子どもに関わりを持つきっかけを作り出している。運営体制も外部の人に開放するなど、教育の「壁」を地域社会に向けてオープンにしているといえる。
生物学者の福岡伸一氏は人間や生物の細胞膜を「流れを遮断するものではなくて、流れを担保するようなもの」だという。完全にオープンでもなくクローズドでもない、人間や自然に近いオーガニックな境界。
これからの建築で求められるのは、そんな細胞膜にも似た「壁」なのではないだろうか。壁によって建築家の自己中心的な「形」をつくるのではなく、境界を自在にコントロールすることで、人や自然、地域社会との「関係」をデザインしなおすこと。未来の建築とは、そこに生まれる多様性を楽しむものなのかもしれない。

本文で触れた対概念の一覧。必ずしもどちらか一方に向かうというのではなく、状況に応じてこれらの境界をコントロールしていくことが、これからの日本では大切になっている。
注3 『境界 ー世界を変える日本の空間操作術』
隈研吾監修 淡交社(2010)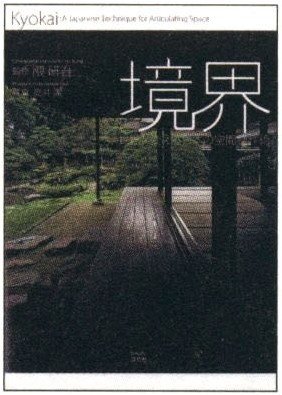
注4 【まちの保育園 小竹向原】
2011年4月、東京練馬に街に開かれた保育園として開園。保育者、保護者、街の人が日々の対話から、創発的に組み立てる保育・教育を目指している。代表は、松本理寿輝さん。
オープンライツ
いつでもどこでも誰とでもつながれる。そんな世界への移り変わりとともに、さまざまなシステムそのもののオープン化も進むだろう。たとえば、著作権の問題。
アニメや映画の違法アップロードに限らず、TwitterやFacebookなどから、誰でも気軽に写真や動画をシェアできるようになっている現在、著作権は「一部のプロフェッショナルの問題」から「国民全員の問題」へと変わってきた。著作権を守ることは重要だが、誰もがプロシューマーになれるインターネット時代において、現状の著作権では足かせになりかねない。
そこで登場したのが、クリエイティブ・コモンズ(注5)のように、著作権の在り方を「禁止」前提ではなく、「自由」から構築し直す動きだ。それは、“All rights reserved”と“No Rights Reserved”しかない既存の著作権システムのなかで、中間領域として“Some Rights Reserved”を提唱する。いわば、個人によって「壁」の高さを調節し、「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」と作品をオープンにすることだ。作り手の権利も守りながら、作品の自由な使用領域を確保し、ダイナミックな「シェア」を促進する仕組み。その元にあるのは、「進化は優れた先人の功績によって生じる」という思想だ。こうした権利をオープンにする動きは、世界的にも美術館や図書館、大学、政府、企業へと広がっている。「Europeana」(注6)では数百万もの本や絵画、映像、彫刻などのデジタルデータが無料で配信され、アメリカのM-T「オープンコースウェア」(注7)では年間5万ドルとも言われる授業のムービーや、講義ノート、試験などを無料で配信している。
その流れは今後、お金を払う「価値」そのものも変えていくだろう。たとえば、坂本龍一が「skmt Social Project」(注8)で高音質ライブ中継を無料で行い、10万人以上のビューワーを集めたことは記憶に新しいが、プロジェクトを通じた販売もi-tunesミュージックストアで上位1位、2位を占めた。これは人々が従来のようにCDという「物」に対してではなく、「体験」価値に対して支払ったものといえる。
オープンライツというシステムが、人々の「自発性」や「モラル」によって支えられていることはいうまでもない。しかし、受動的な消費者としてではなく、自発的な「参加」「好意」「共有」によって支えられる新しいエコシステムは今後も新しい創作物を生む土壌となり、未来のビジネスのあり方までも変えていくに違いない。

注5 クリエイティブ・コモンズ
より自由でダイナミックな著作物の利用を促進するため、インターネット時代の世界共通の新しい著作権ルールを創設する活動団体。権利者は必要に合わせて、4種類の条件からなる6種類のCCライセンスを選ぶことができる。
注6 【EUROPIANA】
人々がヨーロッパの文化や科学上の遺産をシェアできるようにすることを目的に、ヨーロッパ中の美術館や図書館などのアーカイブや映像コレクションを公開していくウェブサイト。
http://www.europeana.eu
注7 【MIT OPEN COURSEWARE】
知識と教育の発展に努力し、21世紀の世界に貢献するというMITのミッションに基づき、世界中の教育者、学生、自ら学ぼうという意欲のある人に向け、MITの全カリキュラムを無償で公開する制度。
注8 【skmt Social Project】
2011年1月より坂本龍一によって開始されたソーシャルメディアを活用した実験プロジェクト。USTREAMによる高音質ライブ中継のほか、映画館など有志のファンの協力による高画質・高音質のパブリックビューイングの開催など、音楽とビジュアル、テクノロジーを調和させて坂本龍一の音楽世界を余すところなく伝えることを目的としている。
オープンソース
オープンソースと言えば、LinuxやAndroidといったソフトウェア開発分野のイメージが強いが、それはインターネットによって可能になった世界規模のマスコラボレーションだ。
「創造は異質のものの組み合わせから生まれる」といわれるなかで、世界中の多様な才能に創造の場の「壁」を開くことで、新たなイノベーションを生む可能性をもっている。
オープンソースには、「無償」「誰でも自由に改良や再配布が行える」という特徴がある。たとえばモバゲーやGREE、Facebookなどは、アプリ開発のフレームワークをオープンソースにすることで、自分たちのプラットフォームに数多くのアプリを集めることに成功している。
またオープンソースは、独裁者が生まれにくいことも特徴だ。たとえばナイキの「Environmental Apparel Design Tool」は、競合他社でも自由に利用することができる。富の独占ではなく、業界の持続可能状態を目的としたこのツールは、ナイキがリーダーになることはあっても、決して富の独裁者になることはない。
ジェフ・ジャービスが著書『パブリック』で「透明性」の重要さを説いたように、外壁をオープンにし、「みんなでより良くしていこう」というリーダーの号令の下で情報を公開して協力しあうことで、持続的に発展するエコシステムが生まれる。
Wikipediaユーザーが編集に使った労働価値の合計は、2009年時点で約7億ドルにのぼると言われているが、これも一つの分野での始まりにすぎない。パブリックでオープンなコラボレーションは今後も企業や研究開発、政府などさらに多くの分野で応用されていくだろう。

ナイキが7年の歳月をかけ、600万ドルを投資して開発・運用しているツール「Environmantal Apparel Design Tool」は、素材やその再生率、オーガニック率、コーティング・ラミネートの有無などを入力すれば、出来上がった製品の環境負荷をリアルタイムに自動評価してくれる。アパレル業界を持続可能な製品づくりへと導くために、誰でも使えるオープンソースとなっている。
http://www.nikeinc.com/news/nike-releases-environmental-design-tool-to-industry

ジェフ・ジャービスは著書『パブリック -開かれたネットの価値を最大化せよ』で、「企業は、自社の価値を、所有物の値段(中略)ではなく、つながりの質で測るようになるだろう。つながりは企業秘密より大きな価値を持つようになるだろう」と述べた。
「β農業」が日本の食を支える
たとえば、農業分野でオープンソース化が進むと、どんな未来が待っているのだろう。
農家が休耕地を複数の希望者に無償でレンタルし、自由に作物を育ててもらう。そして、農家を含めた全参加者が知恵やスキル、意見などを共有しながら作物の品質向上に努める。農家は自分の耕した農地でできた作物に加え、集まったノウハウそのものの売買で生計を立てる。参加者は、それぞれの作物を自由に持ち帰ることができ(販売は禁止)、ノウハウ開発メンバーとして名を残す。双方は領主と小作人の関係ではなく、コラボレーションする立場なのだ。
ソフトウェアのβ版を発表し、ユーザーを共同クリエイターと見なすことでよりよい製品を完成させるかのように、「β農業」ともいえるオープンソースな農業プロジェクトが、未来の日本の食料事情を支える日も遠くない。
まとめ
結局のところ、僕らの考える「オープンになる」ということは、「壁を自由にコントロールできる状態にする」ことだ。それは「個人の確立」を追うあまり、さまざまな分野で細分化が起き、結果的に個人の存在を壁の内側に押し込めてしまった近現代社会からの脱却でもある。この壁を、風を感じる高さ、他人と対話ができる高さ、時にはじっくり考えごとができる高さなど、境界を規定せず、自由にコントロールできる状態にすることこそが、これからの日本に求められるのではないだろうか。
中沢新一氏が著書『日本の大転換』で、社会が本来持っている「人間同士を分離するのではなく、結びつける作用」を「キアスム(交差)」と呼び、その重要性を説いたように、現代の日本は「縁」や「贈与」の精神を失って久しい。大切なのは、交換価値という「無縁の原理」によってそれ自体、自閉してしまった資本主義に自然のもつ「贈与の原理」や人と人、自然との「つながり」を回復していくことだ。それができなければ、「オープンな社会」も常に「無秩序」や「富の独占」、「環境破壊」といった危険にさらされてしまうだろう。
そんな中で、3・11後の活発な支援活動は、まさに2011年が「オープン元年」とも言える現象だったといえる。多数の個人ボランティアやGoogleの「パーソンファインダー」などの例を挙げるまでもなく、資本主義的な市場原理とは異なる力が、大きな存在感を示したのだ。
これからの日本は、国全体を「未来のためのオープンな実験場」と捉え直し、多様な人が多様なリソースを駆使していくことが求められる。そのためには、数値化できる側面だけから物事の価値を見るのではなく、寛容性や信頼を大切にしながら、人と社会、生態系とのつながりや多様性を育み、それこそが「豊かさ」の価値なのだと気づくことが大切なのだろう。
構成・文:近藤ヒデノリ、山内真太郎
撮影:三部正博
▶ この記事の続きを読む
【永井元編集長 渾身の一冊を無料公開】
この記事が掲載されている永井元編集長 渾身の一冊をオンラインにて無料公開します。
『広告』2012年1月号 vol.388
特集「やさしい革命」
▶ こちらよりご覧ください
※2012年1月20日発行 雑誌『広告』vol.388 特集「やさしい革命」より転載。記事内容はすべて発行当時のものです。
いいなと思ったら応援しよう!

