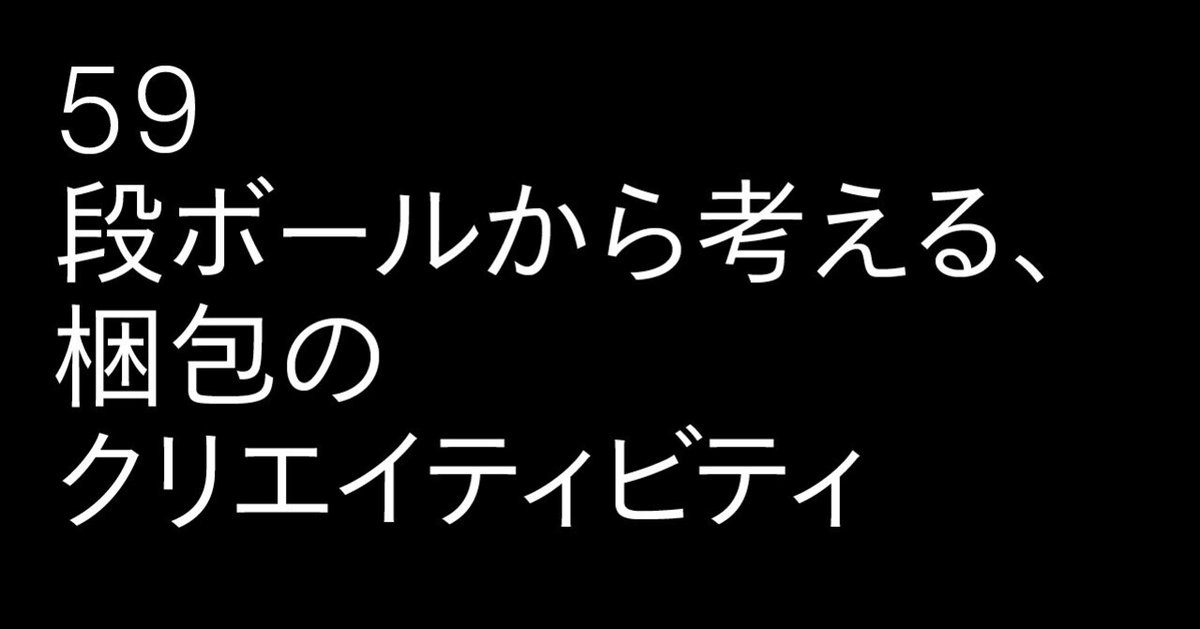
59 段ボールから考える、梱包のクリエイティビティ
コロナ禍のまっただなかにある現在、これまでよりも接する機会が増えたのが段ボールではないだろうか。ネットで購入した商品に始まり、会えない距離にある親しい人に送り、送られる品物まで、安全かつ確実な配送には欠かせない梱包材だ。
今日あまりにも身近な存在だが、そもそもどこで生まれ、なぜ「段ボール」という名前がついたのだろう?
段ボールと段ボール箱の定義
国内における段ボールの定義は、日本産業規格(JIS)の「包装-用語」2019番で明確に定められていた。
2019 段ボール
波形に成形した中芯原紙の片面又は両面にライナを貼ったもの。片面段ボール, 両面段ボール, 複両面段ボール及び複々両面段ボールの種類がある。
──JIS Z0108:2012
つまり、中芯(波状にした板紙)にライナ(平坦な板紙)を貼り合わせた紙の名前が段ボールだ。普段、なにげなく段ボールと呼ばれている箱は、正確には「段ボール箱」と、省略しないのが正解。これは意外だった。
JISではさらに、段ボール箱のことが「押しけいと切り刃とを組み合わせた抜き型で, 板紙又は段ボールを必要な形に切り取って組み立てた箱」(打抜箱、抜き箱)と明確に定義されている。

断熱の用途でコンビニのホットコーヒーに付けるスリーブ。これも立派な段ボール(片面段ボール) 画像:筆者撮影
4種類の段ボールのうち、2枚のライナで中芯を挟んだ「両面段ボール」が、私たちになじみ深いものだろう。ちなみに「複両面段ボール」や「複々両面段ボール」といった特殊な形の段ボールは、重量物の運搬の際などに使われるものだ。

4種類ある段ボールの形状。(A)片面段ボール、(B)両面段ボール、(C)複両面段ボール、(D)複々両面段ボール
日本で段ボールが誕生するまで
段ボールの歴史を辿ると1856年に行き着く。これは英国のエドワード・チャールズ・ヒーレイとエドワード・エリス・アレンが、段(フルート)をつけたボール紙の形状で特許を取得した年。しかし、輸送や包装の目的ではなく、シルクハットの内側に貼りつけて汗を取るためのベルトとして使われた。
片面段ボールの登場は1874年。米国のオリバー・ロングが、ビン類の包装材として特許を取得した。1890年にキャタピラーつき両面段ボール機が考案され、初の段ボール機械メーカーが誕生する。この頃から、接着剤にケイ酸ソーダ(水ガラス)の使用が試みられ、大量生産への道筋が開けた。
日本で段ボールの国産化が始まったのは1909年。井上貞治郎(段ボール業界の最大手・レンゴー創業者)が手回し式の段繰機で、段のついたボール紙を生産。井上がこれを「段ボール」と命名し、電球や化粧品、薬ビン、輸出用陶磁器など、割れやすい商品の緩衝材として販売した。1912年に井上はドイツのミューラー社から片面機と製箱機を輸入。両面段ボールを使って、国内初の「段ボール箱」を生み出した。
飛躍のきっかけは1914年に勃発した第一次大戦だった。ロシア向け電球の輸出に伴い、段ボール箱の需要が急増したという。

井上貞治郎が1909年につくった「段ボール製造機1号」。七輪で温めた上下の金属製段ロールの間へ、ハンドルを回してボール紙を差し込んでいき、波状に成型する。 画像:「レンゴー」ウェブサイトより
関東大震災、太平洋戦争を経て、日本が復興に歩みはじめた1951年6月、森林法の改正で木材の濫伐が禁じられる。木材価格の急騰により、それまで木箱を使用していた流通の現場も、徐々に段ボール箱へ切り替わっていき、段ボール産業の一大発展期が訪れた。
流通の都合で野菜が変えられた
高度成長期を迎えた1960年代。私たちの食生活へ段ボールの普及が意外な形で影響した。従来あった野菜(固定種)と都市化の関係に詳しい、大竹道茂の著書から引用する。
オリンピック景気にも沸く東京では、あちこちで道路や建物の工事が行われていた。(中略)大勢の人が仕事を求めて地方から東京に移り住み、オリンピック前年の1963年(昭和38)には、人口は1000万人を超えた。時代の大きな変化は、東京の農業にも大きな影響をもたらした。大都市に農産物を安定して供給することを目的とした「野菜生産出荷安定法」(1966年)が制定される。(中略)
この法律は大都市に安定的に農作物を供給するために制定されたもので、キャベツ、ダイコン、タマネギ、キュウリ、トマトなど、主要野菜14品目の「指定産地」が決められた。これにともない全国各地に大産地が生まれ、流通や小売業者からは、遠隔地から効率的に輸送できるよう、段ボール箱に収まる規格通りのサイズの野菜が求められるようになった。
──『江戸東京野菜の物語』(凡社、2020年)10頁、13頁より
現在からは想像もつかないような首都の人口爆発、旺盛な食欲を支えるための食料の供給。新しく整備されつつある道路網を使って、段ボールを満載したトラックが列をなして東京へ向かう様が目に浮かぶ。そこではいかに早く、大量に、効率よく品物を運ぶかが求められた。
当時の人々は知恵を絞る。野菜という自然からの恵みを扱うにあたり、工業製品のような規格化が適用できないものか?
固定種の野菜は揃いが悪く、出荷のためにサイズを揃えようとすると6~7割も規格外となってしまう種もあり、規格重視の流通にはなじまない。そこで、種苗業界では揃いのよい野菜や周年栽培ができる交配種を開発して、大量生産を可能とした。
だが交配種は、固定種の欠点を補う性質を一代だけ受け継いだ一代雑種(F1)なので、F1から採れるタネは、親の性質は受け継がない。したがって自家採種はできなくなり、農家は作付ごとに、育苗メーカーからタネを毎年購入せざるを得なくなった。
栽培しやすい交配種への移行がどんどん進み、そのうえ、全国的に農地の宅地化が進んでいくので、東京をはじめ三大都市圏や政令都市など、大都市近郊の生産者は減少を続け、各地に伝わる伝統野菜は次第に栽培されなくなっていった。
──同13〜14頁より
味や品質の改良ではなく、流通の都合に合わせて形を変化させ、農業のあり方をも変えてしまった野菜の歴史。だが、流通をになう段ボールが「画一的なもの」ではなく、テクノロジーの支援によって柔軟に変化する力を備え、しかも経済的なコストを損なわないでいられたら……。
今日なら持てるであろう技術への目線を保ちながら、段ボールそのものの考察に再び戻ることにしよう。
最後までお読みいただきありがとうございます。Twitterにて最新情報つぶやいてます。雑誌『広告』@kohkoku_jp

