
小売が持つべき倫理観とは?
リテールフューチャリスト 最所あさみ × 経済学者 大垣昌夫 × 小野直紀
『広告』流通特集号イベントレポート
2月16日に発売された雑誌『広告』流通特集号にかかわりの深い方々をお招きし、オンラインでのトークイベントを開催しました。今回は、2月26日に青山ブックセンターの主催で行なわれたイベントレポートをお届けします。ゲストはリテールフューチャリストの最所あさみさんと経済学者の大垣昌夫さん。「エシカル」や「サステナブル」が重要視されるいまの時代、「売る」ことを第一優先としがちな小売はどう変わっていくべきなのか。『広告』編集長の小野も加わり、よりよい小売のあり方について考えました。
売り手が不幸を背負う、小売の現状
小野:本日は、リテールフューチャリストの最所あさみさんと経済学者の大垣昌夫さんをゲストにお迎えしています。最所さんは、『広告』流通特集号でふたつの記事でご参加いただいたほか、全体の編集アドバイザーとしてもご協力いただきました。そんな最所さんと相談しながら、今回のテーマ「小売が持つべき倫理観とは?」を考えるうえで「ぜひこの方とお話ししたい」となったのが大垣さんでした。
あらためて僕から大垣さんにお伺いしたいのですが、大垣さんは経済学者として、倫理観や価値観が経済行動に与える影響についての研究をされていますよね。その研究は具体的にどういうものなのでしょうか。経済と倫理って、距離があるように思うのですが……。
大垣:経済学に倫理観や価値観などの「世界観」を取り入れる研究をしています。『広告』流通特集号の「61 アフターデジタルとD2C」という記事のなかに「世界観を売る」という言葉が出てきますが、「世界観」という言葉を最初に提示したのは哲学者のイマヌエル・カントです。カントは、「真の世界は時間の次元がないという意味で永遠で、空間の次元がないという意味で無限である」と言っています。でも、われわれの認識能力はものすごく限られていて、さらに、限られた世界をひとりひとりが異なるメガネをかけて見ています。たとえば、「どんな職業がいいのか?」という問いに対して、ある人はお金や安定を基準に考えるし、ある人はやりがいを基準に考える。このように、メガネの違い……つまり、世界観の違いによって選択は変わるのです。
そうなると、人間にとって世界観はとても重要だと言えます。そして、世界観のなかでいちばん経済行動に影響するのは倫理観だと考えました。それで、“倫理観がどのように経済行動に影響しているか”について研究しようと思ったんです。
たとえば、大災害などで深刻な水不足になり、ある店が500mlのペットボトル1本を1万円で売ったとします。それは市場価格として適正だったとしても、多くの人は火事場泥棒じゃないかと非難するでしょう。では、どのような倫理観では1万円が適正であり、逆にどのような倫理観だと適正でなくなるのか? このようなことを研究しています。
小野:おもしろいですね。とくに昨今だと、小売や消費活動において「エシカル(ethical)」という言葉がよく使われています。大垣さんは、それを先駆けて研究されていた。
最所さんは「知性ある消費」をミッションとして小売や商業全般に関する情報発信をされていらっしゃいますが、今日のテーマ「小売が持つべき倫理観とは?」に対して、どんな問題意識を持っていますか?
最所:私は消費文化の研究や小売のコンサルティングなどをしているのですが、現在の小売業界では売り手が不幸を背負いながら販売するという慣習が強くあると感じています。かつて私が勤めていた百貨店でも多くの販売員にはノルマがあって、その達成のために本心では「このお客様には似合わないな……」と思った服でも「似合いますよ」と言って売ることもある。
最近では、自社ECサイトを通じて顧客に直接販売する「D2C(direct-to-consumer)」がもてはやされています。しかし、そこでも根本的な仕組みは同じです。売ることだけを考えた広告が溢れている。PRしているインフルエンサーの方も「これ、本当に効果があるのかな?」と疑問に思いながら宣伝していることも多いと思うんです。こうした小売の現状のなかで、「どうしたら小売全体の健やかさをつくれるのか?」が、私の大きなテーマです。
今回、『広告』流通特集号の「68 世界的ラグジュアリーブランドのなりたちと展望」という記事で、元エルメス副社長の齋藤峰明さんに取材しました。エルメスは、グローバルブランドとしてあれだけの規模を持ちながら、「売れればいい」という価値観に巻き込まれずに事業展開ができている数少ないブランドです。齋藤さんは、エルメスの第一の目的は、職人の技術を継承すること。そのために、「どのようにものをつくり、売り、伝えていくか」を考え抜いているとおっしゃっていました。こうしたスタイルは、小売業にとってすごく理想的だと思います。倫理観を守りながら規模を大きくするのは、本当に難しいことです。でも、せっかくD2Cが発達して、ブランドと消費者が直接繋がれるんです。従来のように心をすり減らさなくても、商売ができる方法があるんじゃないでしょうか。
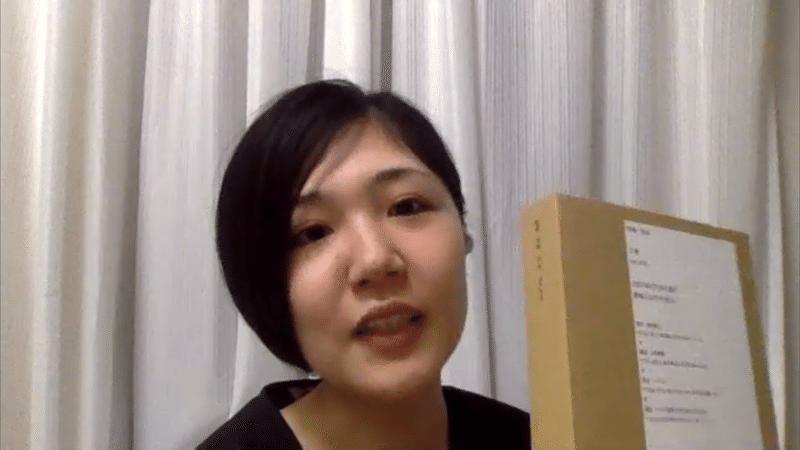
小野:小売業界に限らず、流通全体が効率化・合理化し、より安く、より早く、より多く売るという方向に発展してきた歴史があります。それに対して、昨今は多くのメーカーで「エシカルであること」が重視されていますが、小売業界はいまだに「売ること」が第一となりがちで、それでいいのかという議論があまりなされていないと思うんです。D2Cやスタートアップ企業だけでなく、大手企業が率先して問題提起をしていったほうが、状況はよくなっていくと思うんですけどね。
小売のミッションは、共同体を維持させ助け合うこと
最所:先ほど大垣さんのお話のなかで、「倫理観」という言葉が出てきましたよね。いま小売では「エシカル」や「サステナブル」といった言葉はよく使われているんですが、言葉がひとり歩きしていて「エシカル=おしゃれ」くらいの感覚で認知されている気がします。エシカル(倫理的)とは、そもそもどんな意味なんでしょうか?
大垣:最初から難しい質問ですね(笑)。じつは、倫理観というのはたくさんあります。でも体系化すれば主に3つ。「功利主義」「義務論」「徳倫理」です。
まず功利主義ですが、「幸福」とも「生活満足度」とも言い換えられます。消費したり、余暇が増えると生活満足度が上がるという考え方です。これを経済学者は「効用」とも言うし、ベンサムの「最大多数の最大幸福」とか、「経済効率」という言葉でも表されます。この倫理観のもとでは、プロセスの公平さはどうでもよくて、結果だけを見て、多くの人が幸福であればいいと考える。
次に義務論ですが、これはカントが提唱したものです。カントは、ものすごく崇高な考えを持っていて、徹底的に動機の純粋性を追求します。たとえば義務論の考え方だと、最所さんがさっきおっしゃったような、売るために似合っていないものを「似合っていますよ」というのは絶対にダメです(笑)。この倫理観では動機がすべて。結果的に消費者にとっていいことであっても、動機が純粋でなければいけません。ただ、心のなかは誰にもわかりませんから、動機の純粋性について他人は指摘することができない。そうなると、この倫理観のもとでは、小売業の人に「本当にエシカルであるか?」と他人が問うことはできません。
ちょっと話はそれますが、芸能人が慈善活動をすると「あんなのは偽善だ」という声が出てきますよね。でも、カントに言わせれば、動機の純粋性について、他人がとやかくいうことはナンセンスなのです。
最後に徳倫理について。義務論のように動機の純粋性ばかりを求めれば、多くの人は不純です。世の中は誘惑だらけですから。だから、徳倫理では動機が純粋でなくても、理想に向かって改善していればいいと考えます。徳倫理のいちばんのポイントは、「ミッション」を持つこと。「自分がいまここにいる目的」を考えて、誠実に行動するのです。
小売業にもっとも大切なのは、このミッションだと思います。高度成長期における小売のミッションは成長することでしたよね。でも、いまは違う。災害や少子高齢化など、多くの危機に直面している日本で小売だけ成長したら、それは異常に増殖するガン細胞みたいなもの。危機の時代に必要なのは、成長ではなく維持させることです。あとひとつ、助け合いです。だから、助け合いを促進してコミュニティをつくることも、小売の重要なミッションなんじゃないかな。
最所:小売のミッションがコミュニティをつくることというのは、本当にそのとおりですよね。どんなにECが発達しても、実店舗の価値がなくならないのは、共同体を作る役割があるからだと思います。この30年で、地方で百貨店や商店街が駆逐されて、ロードサイドにはチェーン店ばかりが並ぶようになりました。しかし、私個人は、そこに豊かさを感じません。いくらでも代替のきく存在としてではなく、その土地らしさが感じられるお店、地元の人たちがコミュニティを構築しているところに豊かさのヒントがあるのではないかと考えています。小売は単なる商売ではなくて、その土地の文化を作る役割があるはずなんです。
他人のためにお金を使うと幸福度が上がる
最所:成長することがいいとされていた時代は、目指すものがわかりやすかったじゃないですか。一方で、経済に倫理観を合わせると、何がゴールになるんでしょうか?
大垣:もともと、経済学のゴールは幸福です。ただ、一体、何を自分の幸福とするのか? それが大きな問題です。私自身の例で言うと、私は高度経済成長期に育って、物質的に豊かになればなるほど幸福になると考え続けていました。
たとえば、当時は一家に1台しかテレビがなくて、それが不幸なことだと思っていた。でも、いま振り返れば、テレビが2台あったとしても幸福になったかどうかはわかりません。実際、日本は高度経済成長期に所得がものすごく上がったけど、幸福度は変わらなかった。幸福度に物質的な豊かさはそんなに影響を与えないんですよね。
とある心理実験があります。朝、学生を数人集めて、幸福度をはかるんです。そして、ふたつのグループにわけて、一方には5ドル、もう一方には20ドル渡します。さらにそれぞれのグループ内で、ひとつには自分のためにお金を使ってくださいと指示をだし、もうひとつには他の人のためにお金を使ってくださいと指示を出す。そして夕方、学生の幸福感を再びはかるんです。すると、他の人のためにお金を使ったグループは幸福感が上がっている。一方、自分のために使った人たちは上がってないんですよ。この研究のキモは、実験に参加しない学生たちに「どのグループがいちばん幸福になると思うか?」と聞くと、20ドルもらって自分のために使うグループだと考えるわけ。つまり、われわれは幸福になる方法について大きな勘違いしているんです。実は、他の人たちに寄付やプレゼントをするのがいちばん幸福になれるんですよね。
このことを、アリストテレスは「エウダイモニア(eudaemonia)」という幸福概念で表しています。われわれは共同体に貢献すると、幸福感を感じます。経済学では金持ちになってビーチに寝そべるのが幸福であると考えるんだけど、本当は共同体のためにバリバリ働いたほうが幸福になるんです。だから、倫理的な視点を持って経済のゴールを定めるのであれば、「エウダイモニア」をもっと推奨すればいい。
倫理がお金儲け主義に負けないためには?
最所:なるほど。最近、渋沢栄一の『論語と算盤』を読んだんですが、倫理と経済の両方、バランスをとることが大切なんだろうなと感じました。ただ、小売の現場ではエシカルなミッションを最初に掲げても、規模が大きくなるにつれて、資本主義に飲み込まれてしまってミッションを忘れがちです。大垣さんは、バランスをとるためにどうすればいいと考えますか?
大垣:会社がミッションを忘れてしまうのは、誘惑があるからです。会社が大きくなればなるほど、誘惑は大きくなっていく。ならば、最初に宣言すればいいんです。行動経済学では「コミットメント」と言います。つまり、定款に書けばいい。定款には拘束力があるので、書いてしまうと果たさなきゃいけません。破れば民事に訴えられることもある。そうやって、ミッションで自分をしばっていくわけ。誘惑があるということを念頭において、誘惑に負けるとコストがかかるようにしておく。これが、行動経済学のやり方です。
慶應義塾大学の卒業生がやっている「食べチョク」というサービスがあるのですが、このサービスでは、農家を応援するというミッションを掲げています。この食べチョクの優れている点は、市場メカニズムと共同体のバランスが取れていること。通常、農家はJAをとおして農作物を卸すので、小売価格が決められている。でも、食べチョクでは価格が自由です。市場メカニズムを使いながら、お得感もあって、“農家を応援する”という共同体意識もはぐくまれている。
小野:バランスを取るために、ミッションを宣言するというのは大切ですね。最所さん、現状の小売業界では、どのようなミッションがあるのでしょうか?
最所:そうですね……。たとえば、アメリカのスーパーチェーン「ウォルマート」が掲げる「エブリディ・ロープライス」は有名ですよね。ミッションとは違いますが、ユニクロのものづくりは「ライフウェア」をテーマにしており、ウォルマートと似た姿勢を感じます。上質なものを安く提供して、世の中を豊かにする。これが、彼らのミッションの根源なんだろうなと。
また、私は、髙島屋元取締役の川勝堅一さんの哲学が好きですね。彼は、髙島屋の存在意義は“文化の発展に寄与すること”だと言っています。百貨店はもともと儲かるビジネスモデルではないのだから金銭的な豊かさ以外の価値を創出するべきだと。
こうして比べてみると、設定されたミッションによって顧客層や価格設定、場のつくり方も自然と異なってくるものですね。
小野:僕もひとつ事例を思い出したんですが、サンフランシスコ発のオンラインSPAブランド「エバーレーン」は、「徹底した透明性」をうたっています。どうやって材料を仕入れ、どうやってつくり、どうやって届けているか。すべてのコストを開示している。かれらは、徹底した透明性が社会の価値になると考えているんです。
日本古来の経済倫理「三方よし」の考え方
最所:冒頭で大垣さんは、倫理観は複数あり、世界観は人の数だけあるとおっしゃっていましたよね。いま、企業もエシカルであることが求められていますが、人から借りてきた倫理観や世界観を使用していることが多いと感じています。
エバーレーンの例が出ましたが、彼らはひとつの商品に対して、原価や人件費のパーセンテージをECサイトに記載している。それは彼らが、商品価格に対する内訳がブラックボックスになっていることに問題意識があったからです。でも、その取り組みによってエバーレーンが人気になったため、その手法だけが真似されてしまっています。透明性を発揮することが、単に売れる手法だと思われている。
ミッションを掲げている企業は多くあります。しかし、それでも実現できていないのは、そもそも掲げるミッションが、人から借りてきた言葉でしかないからなんじゃないでしょうか?
小野:社会的に意義のあるミッションをどうやって企業が掲げていくのか……。社会的に意義があり、企業として利益も出せるミッションを立てるには、どうすればいいんでしょうか?
大垣:近江商人の「三方よし」(※1)じゃないでしょうか? 三方とは、売り手、買い手、世間のこと。売り手と買い手だけじゃなくて、「世間=社会」に貢献できてこそいいという意味が込められています。ミッションには、このような日本古来の倫理観を入れていったほうが、借りものにならない。
『広告』流通特集号に「80 『おてんとさまが見てるよ』」という記事がありましたが、“おてんとさまが見てる”というのは、日本的な倫理観です。『菊と刀』の著者として知られているルース・ベネディクトは、「日本は恥の文化、アメリカは罪の文化」と言いました。彼女は恥の文化に否定的で、「恥の文化では、人が見ていなければ悪いことをする」と考えた。でも、彼女は重要なことを見落としていた。日本人はおてんとさまに恥ずかしいんですよ。だから現代においても、おてんとうさまに恥ずかしいかどうかを意識すれば、いいんじゃないのかな。
小野:企業、買い手だけでなく、社会にとって何がいいのかというのを企業が積極的に考える必要があるのかもしれません。おてんとうさまに対して恥ずかしくないかどうかというのもおもしろい視点ですね。
マーケティングとは共同体をよくするためのもの
大垣:ところで、小野さんはマーケティングをどう定義されていますか?

小野:マーケティングの定義ですか? そうですね……ものをつくり、売るということ。それを潤滑にするのがマーケティングだと僕は思っています。
大垣:なるほど、いいですね。なぜそれを聞いたかというと、経済学ではこれが大問題でね。伝統的な経済学では、人間をホモエコノミカス(Homo economicus)と見ていました。経済的合理性にのみもとづいて、個人主義的に行動する人間像のことです。人間は合理的であるから、騙されることもない。
一方、行動経済学は、人間をホモサピエンス(Homo sapiens)と見るんです。われわれホモサピエンスは合理的ではなく、あくまで限定合理的である。そうなると、マーケティングって、“非合理的な人たちを騙して金儲けをすること”という考えにもなりかねない。
だからマーケティングをどう定義するかがすごく問題になってくるんです。大垣ゼミのマーケティングの定義は「顧客との共同体をよくするための企業行動全般」です。そう定義すると、企業が人を騙すことは、マーケティングじゃないわけ。
最所:とてもいいですね。やっぱり、一般的にイメージされる“マーケティング”って、倫理観と相反するものと捉えられている節もある気がします。マーケティングは儲けるための方法だから、企業はときに倫理観のない行動もとってしまうものだ、と。企業が本気でエシカルに取り組もうとするならば、「自分たちにとってマーケティングとは何か?」を各社が考えることが大事なのかもしれませんね。
そういえば、エルメスにはマーケティング部がないと聞きました。マーケティングとは、不要なものにどうにか付加価値をつけて買ってもらうための手法であるから、エルメスには必要ないと。彼らなりに「マーケティング」を定義しているからこそ生まれた文化だと思います。
小野:大垣さんのように、マーケティングを「顧客との共同体をよくするためのもの」として捉え直すのは、大きなヒントですね。邪悪なことをしたら、共同体が成立しなくなる。
『広告』の記事のなかに、転売についてふれた「63 『売る』というエンターテインメント」という記事があるのですが、コロナ禍のマスクの高額転売などがどうして成立するかというと、邪悪なことをしても匿名だと逃げられるからです。街の商店が転売すると「あそこはひどい売り方をしている」と後ろ指をさされる。短期的に売上が伸びても、お客さんの信頼を失って損するんですよね。
最所:あと、企業や小売だけじゃなくて、消費者の意識も変える必要があると思います。たとえば、韓国のカフェって2年持たないと言われています。お客が飽きてしまうから、下手したら半年で変わっていく。オーナーは同じで、外側だけ変えるらしいんです。一時期バズって儲けたお金を、別のトレンドに投資する。
もちろんミーハーなことは悪くないけれど、消費者が企業の努力を棄損している場合もあるんだろうなと。なので、私自身は「知性のある消費」を考えていきたいです。
小野:生産者や株主、消費者といったステークホルダーの倫理観がアップデートしないことには、小売の現状は改善しないんでしょうね。消費者は「だって小売が売るんだもん」、売る側は「だってみんなが買うんだもん」ということでは、邪悪のスパイラルになってしまう。
関係性を広げて、よりよい消費に繋げる
小野:参加者から質問がきているので、いくつか取り上げたいと思います。「劣悪な環境でつくられた安いものと、フェアトレードの高いものが並んだときに、消費者はどちらを選択するのか。消費者の倫理観と経済力、どちらによると思いますか? いまの日本社会はどちらが多いと感じますか?」大垣さん、いかがでしょうか?
大垣:平均的な日本人は、物事を関係性で捉えがちです。顔の見えない相手に対しては、なかなか心が動かないんです。だから、欧米よりもフェアトレードへの関心は弱くなってしまう。でも、上手に関係性をつくれば、その心も動くと思います。たとえば、フェアトレードでハッピーになったアフリカの子どもたちや、かかわった日本人の顔を見せるとか。
小野:そうですよね、カント的な義務論というのは僕たちにはまだ難しい。でも、マーケティングの定義を「顧客との共同体をよりよくすること」としたときに、その共同体の範囲のなかに“アフリカの子どもたち”も含めることができるかもしれない。義務感でやるのではなく、共同体意識を持ってポジティブに。広告会社もそこにコミットできればいいですよね。
最所:関係性ってとても大事だと思います。あともうひとつ、「おしゃれ」も重要なキーワードではないでしょうか? ある経営者の方が「消費者が動くきっかけは、安い・美味い・おしゃれの3つ」と言っていました。この3つのなかで、私はいちばん「おしゃれ」が大事だと思っていて。いま、フェアトレードとかエシカルが、おしゃれなものとして捉えられていて、それが確実に購入するきっかけになっている。パリコレにでるようなブランドもエシカルやフェアトレードを大事にしている時代なんです。確実に評価軸が変わってきていると思います。
このように倫理観か経済力かの二択ではなく、おしゃれだからとか流行っているからという理由で興味を持つ人が増えるのもとてもいいことだと思います。そのうえで、一過性の盛り上がりにしないためにはつくり手や売り手がある意味で消費者を「育てる」ような、より深いアプローチが必要ですよね。
顧客体験のフェーズと消費者の意識
小野:もうひとつ質問を取り上げようと思います。「消費者側が倫理観を考える契機として、顧客体験のデザインはどのような役割を果たすと考えますか? たとえば、倫理的に優れた商品だったとしても、スーパーやコンビニ、アマゾンなどでほかの商品と同じように売っていては、顧客行動は変化しないと思います」と。これはいかがですか?
最所:そうですね。これはフェーズがあるかなと思います。エシカルに限らず、いいものを最初に評価するのは、その分野への意識が高い人たちです。でも、一般流通に乗せてしまうと、ほかの商品に埋もれてしまって意識の高い人たちに見つけてもらいづらくなります。
自分たちの志や背景を知ってもらうには、直接販売でコミュニケーションが取れることが理想的ですよね。ただ、ある程度浸透して、ブランドとして認知されてきたら、次のフェーズとして一般流通にのせることでより広く知ってもらうことができます。どんなにECが発達しても、自社ECの販売比率ってそんなに高くありませんから。なので、はじめは自分たちが直接コミュニケーションを取れる自社ECや実店舗でコアなファンに深く理解してもらい、その範囲が広がったところで一般流通にのせて取り扱ってもらえる場所を増やしていく。
こうして段階を経ることで、伝えたいメッセージを自分たちだけでなく根強いファンにも語ってもらうことができ、メッセージが薄まることなく広まっていくと思います。たとえばiPhoneも初めはおしゃれなガジェット好きがこぞって購入したからこそ、あまり詳しくない人も憧れて一気に顧客層が広まりましたよね。iPhoneが一般的になってからもアップルのメッセージが薄まることなく顧客に受け止められているのは、ブランドを理解したファンがアップルの哲学やスタイルを語り継いできたからだと思います。つまり顧客が「どこで出会うか」「どんな情報を得るか」といった体験をフェーズごとに想定し設計することが流通戦略のひとつの要なのではないかと私は考えています。
小野:「80 『おてんとさまが見てるよ』」の記事に、アメリカのスーパーマーケット「ホールフーズ・マーケット」の話が出てくるんですが、そこでは生育環境によって鶏肉のランクが変わってくる。のびのびと育てられたのか、そこそこの環境で育てられたのかなど、味だけでなく動物愛護の倫理観がそこに反映されていて、消費者に選択肢を与えている。ホールフーズは、消費者にそういう選択肢を与えることを、小売の役割だと思っているんだなと。
倫理的な商品を選ぶことって正直めんどくさいんですよね。逆に言えば小売はそのめんどくささを引き受けて、商品の意義を伝える役割を持つことができる。
コロナ禍で改めて問われる実店舗の意味
小野:最後にもうひとつ参加者からの質問を。「コロナ禍では、対面販売が難しくなっています。顧客と企業の接点であるタッチポイントを対面でつくれないことについて、どう捉えていますか?」最所さん、いかがでしょうか?
最所:そうですね、現在は、対面で接客しづらいことで改めて、実店舗の意義も問われています。でもそもそも、接客ってお客様にとってわずらわしいものでもあるんですよね。知らない人が急に声をかけてくるなんて、よく考えたら変じゃないですか(笑)。 私も販売員をしていたときは、毎日飛び込み営業をしているような気持ちでした。
だからこそ販売員時代の私は、来店前にお客様の情報が欲しいと思っていました。いつどんな目的で来店されるのか、これまでどんな商品を購入して、普段は誰が担当としてついているのか。顧客であればある程度記憶している情報はありますが、新規のお客様にいたっては事前情報はまったくない状態です。お互いの情報をもっと知っていれば、販売員はお客様にとってよりよい商品を提示できるし、お客様も怖くないじゃないですか。本来、人と話すってとても楽しいことのはずなんです。だからオンラインで事前にカウンセリングをしたり、来店予約ができたりすれば、店舗のコミュニケーションももっと豊かなものになるかもしれない。
コロナ禍でこうしたオンラインの施策をはじめたブランドも多く、店舗におけるオンラインとオフラインの融合は今後急激に加速していくと思います。そうなると実店舗の意義が問題になりますが、私はより「コミュニケーションの場」としての側面が強くなっていくと思います。買い物はひとつの娯楽なので、購入に至るまでのプロセスの価値はなくならないはず。対面かどうかにかかわらず、コミュニケーションを通じて豊かな買い物体験をつくれるかどうかが重要だと思っています。
この点は、この会の主催である青山ブックセンターの店主・山下さんにもお話を伺いたいです。
山下:そうですね……。コロナでリアル店舗の価値が薄れたと言われたりしますが、現場の意見としては、やっぱり必要なんじゃないかと強く感じています。便利さの追求は際限がないですし、アマゾンなどの大きな資本には敵いません。それじゃあ、みんながそれを好きなのかというと、そうではない。例に出して恐縮ですけど、全員がユニクロを好きなわけではありません。全部いっしょくたになるのは、個人的にはおもしろくないなと思います。
そこで、小売の倫理とか近江商人の「三方よし」とかは考えなきゃいけないんだろなと。どうしても利益に引っ張られるし、もちろんオンラインも必要なんですが……。とくに本屋はお客様との相性がすごく大事で、色がはっきりしていないと生き残れません。開いていきながらも、お店側からもっと発信して、お店とお客様とのミスマッチも減らしていきたいです。
今回、『広告』のつくり方を見て、つくり手にこういうふうに提示してもらったら、「売り手も頑張らなくては」と背筋が伸びました。小売は流通の最後の出口です。でも、お客さんにとっては、大事な入り口なんですよね。
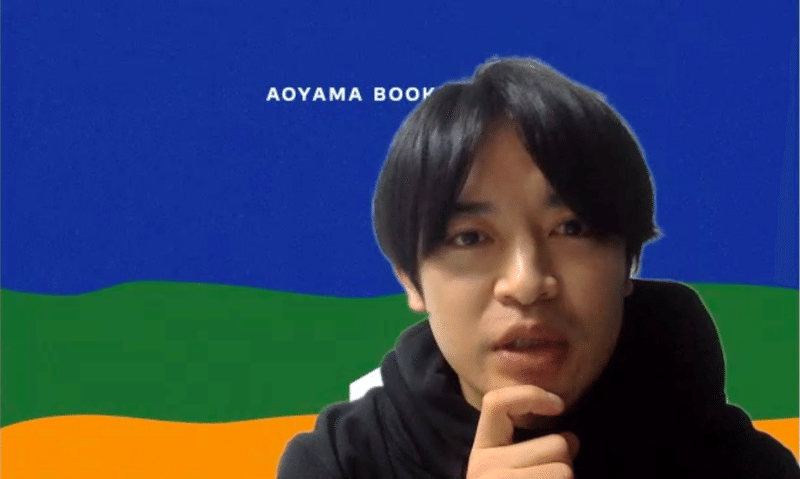
最所:本屋さんがただ売ることを考えたら、いまなら入り口のところに『鬼滅の刃』を並べておけばいい。ほかにも、ベストセラーでセンセーショナルなものとか、愛国心だけを煽るようなものとか。そういえば、青山ブックセンターはヘイト本を置かないと聞いたことがあります。
山下:そうですね、貶めている本はおかないと決めています。見かけるお客さんにとっても苦しいだろうし、届ける自分たちも虚しいですし、加担したくないですから。でもそうすると「じゃあ、あの本はどうなんだ」という意見もいただくので、難しいんですけど。
最所:青山ブックセンターは、書店員が目利きをさせた本が並んでいるという信頼感がありますね。売れ筋だけ見るならアマゾンでいい。
山下:本を売りたいだけなら、実店舗は必要ないのかしれません。よく言われる「売れ筋」というのは、どこかで売れた本のことです。もちろん、売れている本も仕入れます。でも、どこかで売れたものを、「なんでわざわざ、うちでフィーチャーしなくちゃいけないんだろう?」というのは考えるべきだと思います。バランスが大切なんですよね。
実際、うちの年間ランキングって、独特です。全国的なものと全然一致しません。お店の色を確立させるのは、時間がかかります。日々のお客さんと向き合うことが、商売の基本なんですよね。
最所:私はつねづね、小売はアクセラレーターでなければならないと考えてきました。青山ブックセンターさんはまさに「自分たちのカラーがあることで、ほかでは売れなくてもうちなら売れる」という小売店の価値を理想的に体現されていますね。
小野:とくに山下さんは発信し続けている方だと思いますので、小売の現場の声をぜひまた別の機会にもお聞かせください。本日はありがとうございました
文:東江 夏海
大垣 昌夫 (おおがき まさお)
経済学者。慶應義塾大学経済学部教授。1958年生まれ。大阪大学卒業。アメリカ・シカゴ大学経済学部博士課程修了(Ph.D.)。アメリカ・ロチェスター大学助教授、アメリカ・オハイオ州立大学教授等を経て、2009年から現職。2015年から2017年まで行動経済学会会長、2020年から日本学術会議会員。著書に『行動経済学──伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して』(大垣昌夫・田中沙織、有斐閣、2014年)などがある。
最所 あさみ (さいしょ あさみ)
リテールフューチャリスト/キュレーター。大手百貨店入社後、ベンチャー企業を経て2017年独立。ニューリテールにまつわるコンサルティングや執筆、コミュニティマネジメント、イベントプロデュースを行なう。またnote有料マガジンを通して独自の考察や海外事例の紹介、小売や店舗を軸にしたコミュニティ運営を行なう。2019年7月よりnoteプロデューサーに就任。ブランドや店舗オーナーがnoteを通して発信し、顧客とコミュニケーションをとる活動全般を支援する。
東江 夏海 (あがりえ なつみ)
ライター・編集者。沖縄県生まれ。編集プロダクション勤務を経て、独立。看護師・保健師資格を持ち、社会福祉・医療健康の分野を得意とする。関心分野は「ポップミュージックと社会」、「外国人労働者問題」など。agarien0607@gmail.com
脚注
※1 大坂商人、伊勢商人と並ぶ日本三大商人のひとつ、近江商人の心得。売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商売であるとした。
【関連記事】
雑誌『広告』流通特集号で、最所あさみさんにご協力いただいたふたつの記事を全文公開しています。
67 グローバル流通の苦難と挑戦
▶︎ こちらよりご覧ください
68 世界的ラグジュアリーブランドのなりたちと展望
▶︎ こちらよりご覧ください
最後までお読みいただきありがとうございます。Twitterにて最新情報つぶやいてます。雑誌『広告』@kohkoku_jp
